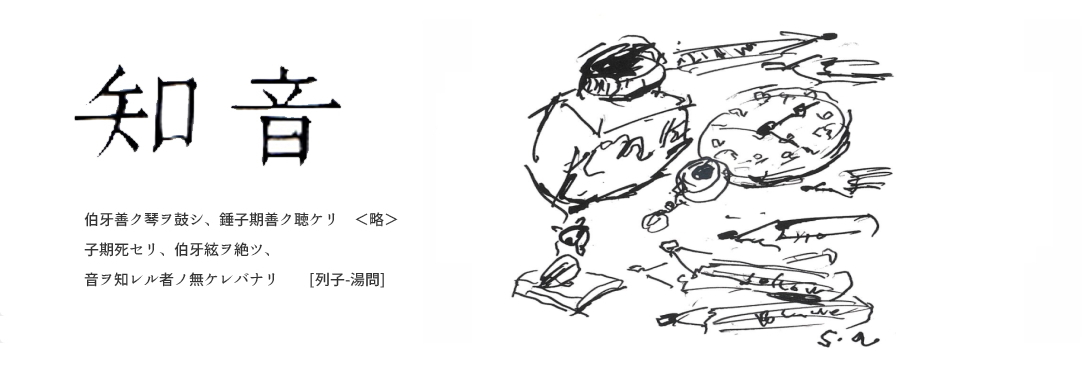月幾夜 西村和子
悼 深見けん二先生
かんばせの老いて涼しき大人なりき
小望月かの世の句座も始まるか
月しろや修道院の空不穏
陰膳の整ひたりし月今宵
名月や瓊の帯なす六玉川
月明や地上に今も神隠し
冷蔵庫ひらけば灯るマスカット
子別れの鴉朝より声荒げ
生身魂 行方克巳
うそぶいて昔男や生身魂
なにがしの受領たるべく生身魂
ものを言ふ口元ほぐれ生身魂
痛いところどこにもないと生身魂
ささめごと昨夜のごとく生身魂
陰撫するごと墨磨れと生身魂
チョコレートはゴディバにかぎり生身魂
てんしきの五連発とは生身魂
濡れ縁 中川純一
灯りたる電車が滲み秋の暮
秋蝶の翅に大きな目のふたつ
糸瓜忌のわが濡れ縁の日差かな
蛛と飛んで蠅虎の馴れなれし
虫すだく教員室はまだ灯り
就中新酒の中の冷おろし
渡り鳥天気予報の空を飛ぶ
秋風や雲も背伸びを思ひきり
◆窓下集- 11月号同人作品 - 中川 純一 選
秋日傘今日の一歩へ開きけり
大村公美
送鐘一打のしがみつくやうに
米澤響子
風鈴や遺品と芥選りわけて
井出野浩貴
原爆忌都庁の窓を雲疾く
小倉京佳
夢二忌や女将と呼ばれ五十年
金子笑子
夏雲やコタンに残る蝦夷錦
佐藤寿子
素通りの縁切寺の蚊にさされ
永井はんな
菊花展巴の錦艶やかに
平野哲斎
船頭の顎で指したる浮巣かな
前田星子
梅雨明くる宵山の空押し広げ
板垣もと子
◆知音集- 11月号雑詠作品 - 西村和子 選
噴水の起承転結見届けぬ
志磨 泉
チボー家のジャック遥けし夏休
井出野浩貴
サングラス外し海風吸ひ込みぬ
くにしちあき
動物園何処にゐても椎香る
大橋有美子
裕次郎灯台目指し船遊び
栃尾智子
烏瓜秘技を尽して咲きにけり
米澤響子
草むしり不器用なれど几帳面
中津麻美
亀の子が玄関先に雨あがり
井戸ちゃわん
型紙を合はせじょきじょきあつぱつぱ
磯貝由佳子
嫌はれてしまへば気楽サングラス
天野きらら
◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子
帰省子の披露上腕二頭筋
志磨 泉
「上腕二頭筋」とはいわゆる力瘤。夏休みに久々に帰ってきた息子さんが、家族みんなに「見て見て、すごいだろう」と腕をあらわにして力瘤を見せつけているのだ。クラブ活動かアルバイトの力仕事か、親元を離れて数か月過ごした間に見違えるように日に焼けて逞しくなった我が子を見あげているのだ。当人は無邪気に自慢しているだけだが、親にしてみればあんなにひ弱だった子がと思うだけで感無量だ。
こうした光景はどこの家でも見られるかもしれないが、作者の人生にとっては今しか詠めない句だ。自分が育てた息子であるからこそ、小さい頃の思い出が二重写しになるのだ。また、親元を離れて過ごすことが初めての我が子であれば、親の心配は尽きない。
丹精の枇杷に疎漏な袋掛け
栃尾智子
町中でよく見かける枇杷にわざわざ袋掛けはしないので、園芸を仕事にしている人の枇杷かとも思われるが、最後まで読んでみると、やはり素人の庭先であることがわかる。それもたわわになっている枇杷ではなく、庭に数えるしかなっていない枇杷であろう。枇杷の花が咲くのは冬。それから何か月も経ってから実がなるのは、果物の中でも珍しく気長だ。その間、今か今かと実が太るのを楽しみに肥料をやったりしていたのだろう。やっと実が大きくなってきたというので、大事を取って袋掛けまで施した。それが疎漏というのではあまり役にたちそうにない。そんなところにおかしみを感じる句である。
「丹精」という言葉と「疎漏」という表現の対比がもたらす俳諧味である。
眼に効くと聞けば毎日パセリかな
井戸ちゃわん
家居が続くこの頃、人々の関心は内へ内へと向かっている。家中を片付けたり、健康食に凝ったり、免疫力を高めると聞けば買い込んだり。私達庶民の日常と人情を実によく表している句だ。テレビか新聞でパセリが眼に効くと知ったのだろう。老眼が気になってくる年代には、聞き流せない情報だ。折しもパセリが大安売りだったのだろう。たくさん買い込んできたものの、新鮮なうちに食べなければ意味がない。毎日食卓に上ることになる。だれもが思い当たることなので、この句から湧き上がる笑いは自嘲も含まれている。
私もスーパーでたくさんのパセリを買い込んだが、みじん切りにして容器に詰めて冷凍したところ、長いこと使えることに気付いた。ぜひお試しあれ。