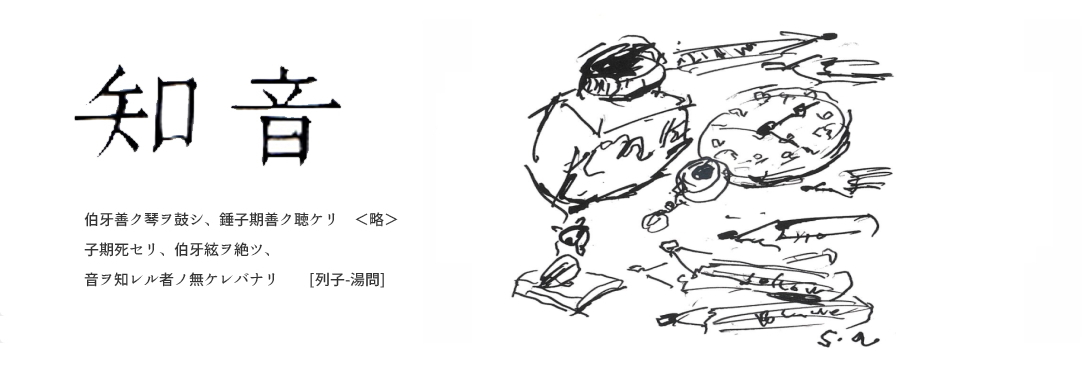滝 西村和子
小さきを水尾にかばへり通し鴨
すでにして滝音届く木の根道
滝五裂十裂千々に砕けたり
滝風に打たれしのみに怯みたり
滝行の頭と見ゆる巌かな
爪先をきちきち刻み神輿舁く
神輿集め雨の洗礼浴びせたり
東京の夜空初々しき五月
雨 蛙 行方克巳
前線に躙り寄りけり雨蛙
少年の眉目寄せたり雨蛙
これ以上近付かないでと雨蛙
ぎしぎしや昔極刑村八分
大方は散るべく咲いて柿の花
鰻屋の婆の口上世知辛く
鰻重の御重の蓋の松と梅
父の日も蕎麦焼酎の蕎麦湯割り
筒 鳥 中川純一
筒鳥や乾きそめたる草踏んで
遠足やをとこ走りに女の子
浅間噴きアイスクリーム濃く甘く
もんどりを打つて鯉幟の父さん
楡若葉吹き抜け帽子攫ふ風
どくだみが咲くどんな世にならうとも
定年の後にもありし五月病み
◆窓下集- 7月号同人作品 - 中川 純一 選
行春やたたむ和服の日の匂ひ
山田まや
春宵の米粒ほどのピアスかな
吉田林檎
レントゲンに映る血栓春寒し
田代重光
天ぷら屋しながき手書きふきのたう
吉田泰子
生きてゐる証の木の根明きにけり
谷川邦廣
すかんぽや里に親無く家も無く
吉澤章子
そぼ降れる癌病棟の花の雨
八木澤 節
交番に大人の迷子春の宵
三石知左子
すかんぽや川沿ひに旧る町工場
青木桐花
トラムにも坊つちやん列車にも落花
松井洋子
◆知音集- 7月号雑詠作品 - 西村和子 選
つばくらや雨の城下の黒瓦
井出野浩貴
五十年経てば骨董春灯
高橋桃衣
孫弟子の老いて華やぐ立子の忌
藤田銀子
戒名のやうな俳号四月馬鹿
影山十二香
信仰に闘ひの日々松の芯
牧田ひとみ
括られしより生き生きと豆の花
松枝真理子
駅弁の酢の匂ひ立つ夏隣
田代重光
春昼の画廊の棚の砂時計
中津麻美
九十一の春欲ばらず生かされて
山田まや
吹かれては三色菫ウインクす
吉田泰子
◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子
さへづりのけふは姿を見せにけり
井出野浩貴
春になって百千鳥の声が耳を楽しませる頃、雀や鶯とは違って耳新しい囀を降り注いでくれる小鳥がいる。この鳥はいったい何だろう、どんな姿をしているのだろうと以前から気になっているが、一向に姿を見せない。そんなことが誰にもあると思う。
この句のポイントは「は」一音である。いつもは声だけで親しんでいる存在が、今日は珍しく姿を見せた。その発見の喜びが一句になった。昨日も一昨日も囀を聞いているのに、今日だけその姿を見た。他から区別して際立たせる場合の「は」である。
ぱかんぽこんかぱんこつぽん港春
高橋桃衣
同じような擬音語でありながら、よく読んでみると、全て違う。動詞が一つもない。でもこれだけで、のどかな漁港の春の昼間であることが描けている。港といっても横浜港や神戸港ではない。船と船が小突きあったり、杭にぶつかったりする音を、ひとつひとつ聞き取って描き分けている。その工夫を読み取りたい。
花水木夕暮は母寂しがる
影山十二香
高齢のお母さんだろう、日の暮に寂しい思いをするのは、働き盛りや子育て最中の年代にはわからない感情かもしれない。人生の一般的な仕事をやり終えて、夕暮の時間を持て余す年代になると、ふと寂しさが襲ってくる。そんなお母さんを思う情が伝わってくる作品だ。
これが秋の夕暮だと付きすぎになるが、ようやく日も長くなって街や庭に花水木が咲く季節に詠んでいる点に注目した。「花水木」は本来の水木の花ではなく、アメリカ花水木である。私の住む町にも街路樹として植えられ、白い花びらがひらひらと風に揺れる様は、人の心も明るくする。明治四十五年東京市長だった尾崎行雄がワシントン市に寄贈した桜の苗木の返礼として、大正四年に贈られてきたそうだ。百年経って東京の街にもすっかり根付いた。
この季語によって、お母さんが深刻な寂しさに囚われているのでもなく、めそめそしているわけでもないことが語られていよう。