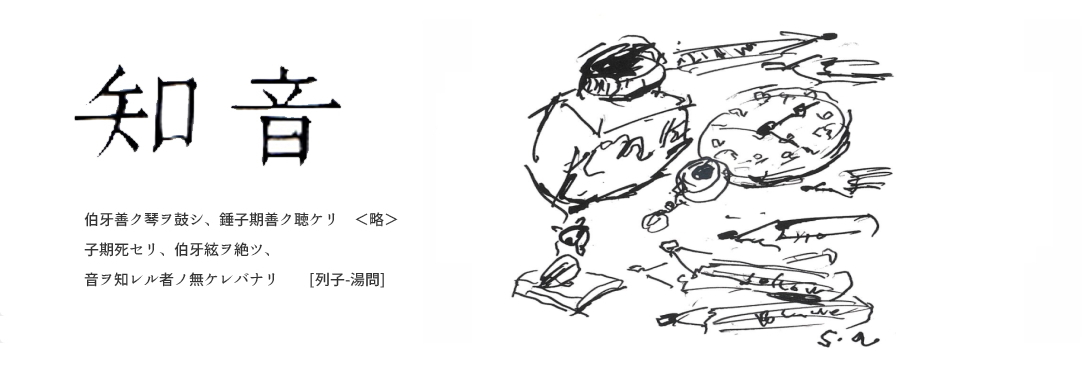北 海 西村和子
朝まだき乗継空港春いまだ
いちはやく春風察知管制塔
地平まで田園霞む離陸かな
拳上げ意気軒昂や大枯木
飛行機雲縦横斜め春浅き
春遠からじ北海の潮境
寒風はぶつかり潮目混りあふ
窓競ふ右岸左岸の冬館
旅ひとり 行方克巳
料峭やことばさがしの旅ひとり
日めくりのあつけらかんと二月尽く
若布刈舟息つぐごとく傾ぎけり
文庫本忘れな草を栞りけり
雛あられむさぼるごとし老いぬれば
てのひらの残像として雛あられ
ガラスペンもて描く未来卒業期
梯子一つ一つ外され卒業す
巣 箱 中川純一
出展の油彩仕上がり春立ちぬ
バレンタインデーのパンプス鳴らし来
東京を吹き飛ばしたる春一番
弁当に輝く卵春立ちぬ
囀の八連音符小止みなく
白梅に目白の逆さ縋りかな
まだ覗かれずあり新しき巣箱
霜柱扇びらきに倒れたる
◆窓下集- 4月号同人作品 - 中川 純一 選
初鏡背ナより妻に覗かれて
小野桂之介
遺伝子のつくづく不思議初鏡
松枝真理子
二階まで行つたり来たり小晦日
佐瀬はま代
初鏡かの世の人の声のして
佐貫亜美
松過ぎのほこりしづめの雨となり
影山十二香
簪のくれなゐ仄と初鏡
清水みのり
幼子の声よくとほり三が日
大塚次郎
チアリーダーどつと乗り来る七日かな
小塚美智子
鉋屑くるくる日脚伸びにけり
井出野浩貴
振り子めく自問自答の冬ざるる
岩本隼人
◆知音集- 4月号雑詠作品 - 西村和子 選
枯蓮たふるることもあたはざる
井出野浩貴
蒼穹を引つ掻き鵙の去りにけり
藤田銀子
鳥海山静かに在す小春凪
石田梨葡
しばらくの閑話に炉火の蘇る
山田まや
寒禽のしぼり切つたる声放つ
米澤響子
神の留守電話の声のしよぼくれて
𠮷田泰子
にほどりにむつかしき顔見られけり
立川六珈
試みの一句も投じ初句会
松枝真理子
夜半の冬初学のノート読み返し
田中優美子
花壇には入れてもらへず石蕗の花
三石知佐子
◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子
亡びしか亡ぼされしか冬の月
井出野浩貴
廃墟を冬の月が寒々と照らしている光景を想像した。国の内外を問わず、かなり文明や文化が発達した痕跡のある場所が、今は廃墟になっていることがよくある。何らかの理由で自ら亡びたのか、外敵に亡ぼされたのか、歴史の奥へ思いを馳せている句と読んだ。
数年前の疫病の世界的流行の折、ウイリアム・マクニールの「疫病と世界史」を読んだ時、今までの世界史観が覆された思いがした。文明や武器が発達した国が、未開の民族を亡ぼしたと思っていたものが、実は免疫のない国へ疫病を持ち込んだことで、民族が亡びてしまったという歴史があったことに、それまで気づかなかった。
この句はかなり抽象的なことを言っているようだが、冬の月に照らし出された廃墟を思い浮かべることができる、深い作品だと思う。
たま風や逃げ足早き波頭
石田梨葡
「たま風」とは、日本海沿岸に西北から吹く季節風。「たま」とは、西北に集まって住む「亡魂」のことで、柳田国男の説によると、この悪霊が吹く風の意味、と歳時記にある。「たま風六時間」と言われ、それほど長続きしないそうだ。山形県在住の作者ならではの作品。
「雪迎へ」とか「白鳥」とか「地吹雪」などとともに、地元の人しか体験できない季語を、もっと積極的に詠んでもらいたい。この句の勢いと速さは、長続きしない季節風を実に的確に描写している。
ポップコーン匂ひスケートリンク開く
𠮷田泰子
子供たちが集まる、冬場だけ開かれる臨時のスケート場であろう。私の住む二子玉川にもあるので、この光景は非常によくわかる。ポップコーンといえど、最近はキャラメル味やチョコレート味が人気らしく、休日の昼間はその香りが満ち満ちている。スケートと言っても、上手な子たちが幅を利かせているわけではなく、全くの初心者が楽しんでいる場所であろう。そうした場所柄を嗅覚によって描いた点が、この句のポイント。