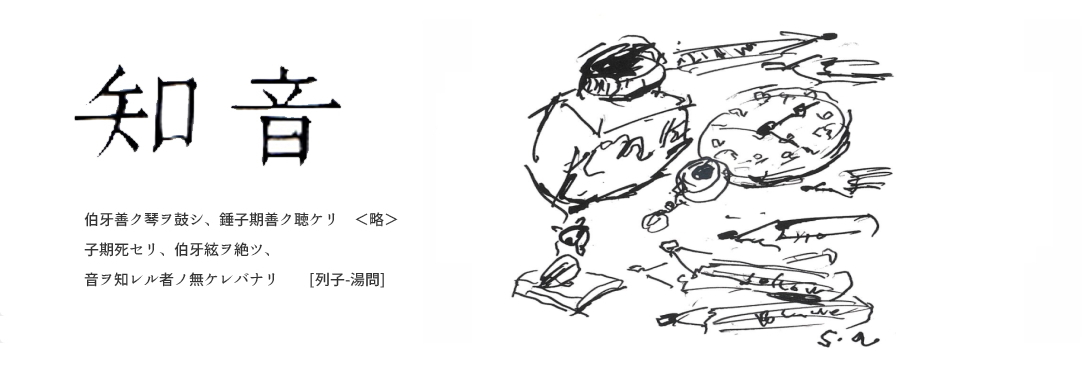◆特選句 西村 和子 選
流氷の来たなと婆の言ふ寒さ
山内 雪
【講評】接岸は何時と毎年ニュースになる流氷。接岸するや、流氷原となった海を眺めに、砕氷船に乗りに、観光客はやって来る。しかしそこに暮らす人々にとっては、波音の無くなった海から押し寄せてくる寒さをじっと耐えなければならない時なのである。
「婆」という言い方から、その地にたくましく生きている人が見えてくる。冬の寒さも知り尽くしている人の覚悟とも取れる一言だからこそ、尋常でない寒さも伝わってくる。(高橋桃衣)
薄氷に風の記憶と夜の記憶
小野 雅子
【講評】池などに張った氷は、木の葉や泡や泥などを包み込んでいるが、この薄氷は凍っていった時の記憶も閉じ込めているという。表面を波打つように凍らせる風の鋭さ、厚みを増して凍っていく夜の静寂、空の星の輝き……木の葉や泡を解き放つように、それらの記憶も少しずつ手放しながら、春の日差しに解けていく薄氷である。(高橋桃衣)
春の野に開く「純情小曲集」
山田 紳介
【講評】 「ふらんすへ行きたしと思へども…」など教科書で習った懐かしい萩原朔太郎の詩集である。「じゅんじょうしょうきょくしゅう」と声にして読めば、拗音のやわらかいリズムは心地よく、「小曲」からは、次々と軽やかな音楽が聞こえそうだ。
今作者は若草の野に来ている。手にした詩集を開けば、序に「やさしい純情にみちた過去の日を記念するために」とある。それはまた作者にとっても、やさしい純情にみちた過去の日を思う時間でもある。(高橋桃衣)
へらへらとつくろひ笑ひみずつぱな
黒木 康仁
【講評】水のように薄く流れ出る鼻汁。寒さで出ることもあるけれども、大の男が水洟を垂らしているのは侘しい。それに気づいて、つくろい笑いするしかない。なんとも情けないなあと、自嘲している様子を「へらへら」という擬態語で描いている。
へろへろとワンタンすするクリスマス 秋元不死男
ひらひらと月光降りぬ貝割菜 川端茅舎
鳥威しひかひかひかときらめける 清崎敏郎
ちかちかとはたゆらゆらと灯涼し 西村和子
など、オノマトペは効果的に使うと感覚的に本質を描き出すことができる。(高橋桃衣)
新玉葱しゃりしゃり刻み母元気
小野 雅子
【講評】玉葱は収穫してからしばらくの間は風にあてて乾燥させるが、新玉葱は早取りしてすぐに出荷するので、水分が多く、皮が薄くてやわらかい。その新鮮さが「しやりしやり」から伝わってくる。しかも生で食べると血圧を下げると言われる玉葱である。巷に出た新玉葱を早速買ってきて、刻もうと台所に立つ母親の気持ちの張りも見えてくる。(高橋桃衣)
◆入選句 西村 和子 選
( )内は原句
仁左衛門の献梅早も真白なり
松井洋子
冴返る遺族年金申請書
田中優美子
遠つ国の歌なつかしき春の鳥
小野雅子
春昼のバス一人乗り二人降り
箱守田鶴
針供養男はカメラ持つばかり
長谷川一枝
一瞬を生きよと光る寒昴
田中優美子
梅の蕊びびびびびびと風の中
三好康夫
包装紙きれいに畳み春隣
森山栄子
囀りや子供のゐない公園の
箱守田鶴
どこからか校歌流るる春野かな
山田紳介
指さしてこれは椿と子に教へ
長谷川一枝
春昼や無音テレビの診療所
中村道子
鳥の影騒ぎ桜の芽の静か
箱守田鶴
いぬふぐりあの日の海の色したる
田中優美子
迸ること楽しくて春の川
小野雅子
丸太積むトラック冬の靄を来る
山内 雪
嘴の濡れてきらきら水温む
藤江すみ江
奥山を越えて降り来し春の雪
黒木康仁
宿坊の絨毯厚く春寒し
鏡味味千代
下ばかり見て下萌に気づきけり
田中優美子
菜の花や雨の予報の誤たず
三好康夫
追ひかけてゐるのはどつち春の野に
山田紳介
春浅し優しい嘘もやはり嘘
鏡味味千代
息抜きが本気になりて春の宵
長谷川一枝
針納めメリケン針と呼びしもの
箱守田鶴
春浅し岩根の声の密やかに
鏡味味千代
(岩々の声密やかに春浅し)
まだ寒さが緩んでない浅春。上五に持っていくと、より締まった感じになります。
折小さき海鮮弁当春めけり
藤江すみ江
(折小さし海鮮弁当春めけり)
海鮮弁当の折が小さいのですから、上五で切らずに続けましょう。
真夜中の冬満月の明るさよ
深澤範子
(深夜二時冬満月の明るさよ)
時間を説明せずに、深夜の雰囲気として詠みましょう。
枝打ちの母の鉈音日脚伸ぶ
田中優美子
(枝打ちの母の鉈の音日脚伸ぶ)
鈴、笛、虫など心に訴えるように響いてくるものは音(ね)、鉈は(おと)です。
絵馬堂の軒をはみ出し盆梅市
松井洋子
(絵馬堂の軒を余りて盆梅市)
「余り」を「はみ出し」としますと、より具体的で、情景が目に浮かびます。
被災地にすつくと立ちて桃の花
深澤範子
(被災地やすつくと立ちて桃の花)
「桃の花」に焦点が絞られるように詠みましょう。
試験中降る雪の音聞こえさう
小野雅子
(大試験降る雪の音聞こえさう)
音なく降る雪の音が聞こえそうなほどの静かさを詠んでいるのですから、中心になる季語は「雪」にしましょう。
羽田発つ窓を流るる春ともし
辻 敦丸
(羽田発つ機窓流るる春ともし)
「羽田発つ」で飛行機だろうと想像できます。
とりあへず明日は生きむ春の星
田中優美子
(とりあへず明日は生きる春の星)
「生きむ」は生きよう、という自分の意志、決意です。
◆互選
各人が選んだ五句のうち、一番の句(☆印)についてのコメントをいただいています。
■鏡味味千代 選
くるくると回る仔犬や春近し 宏実
春寒や誰にも会はぬ散歩道 道子
都会へのあこがれ少し受験生 雅子
嘴の濡れてきらきら水温む すみ江
☆春の夜の心して書く手紙かな 道子
心して書く手紙は夜になることが多い。心の内を吐露したい時には特に。1人の時間にじっくりと。
春の夜とあるので、内容は何か嬉しい便りなのか。もしくは、大事な人へしたためているのか。
■三好康夫 選
春寒や誰にも会はぬ散歩道 道子
丸太積むトラック冬の靄を来る 雪
春隣みやげ屋並ぶ女坂 洋子
恋猫の声の真似して爺と婆 雪
☆包装紙きれいに畳み春隣 栄子
丁寧に詠まれていて、気持ちが良い。
■小野雅子 選
春浅し岩根の声の密やかに 味千代
水鳥のほどよき距離を保ちけり 栄子
包装紙きれいに畳み春隣 栄子
三月十一日また降り積もる春の雪 範子
☆春立つや万葉集の相聞歌 一枝
相聞歌といえば額田王と大海人皇子を思い浮かべる。この二人と天智天皇はややこしい関係。
人目もはばからず歌ってのけた二人を人びとは支持し、歌が万葉集に収められた。
相聞歌を読むと私たちも万葉人に連なっているのだと思う。
さあ春だ。近江の蒲生野にも草が萌え始める。
■藤江すみ江 選
どこからか校歌流るる春野かな 紳介
ブロンズの麒麟の背に春の雲 洋子
その色も被り心地も春帽子 田鶴
絶望も希望もなくて寒オリオン 優美子
☆春隣みやげ屋並ぶ女坂 洋子
季語の春隣に内容がぴったり合っていて、自然に風景が浮かびます。
■箱守田鶴 選
寒椿卒寿へ廻す回覧板 洋子
絎台の小さき針山針供養 朋代
迸ることたのしくて春の川 雅子
冴返る遺族年金申請書 優美子
☆枝打ちの母の鉈音日脚伸ぶ 優美子
この庭木の枝打ちは長年母の仕事、いや、趣味だったかもしれない。
とはいえ鉈を使うには高齢だ。
少し日が伸びたからこそ決心して始めたのだろう。
だがいつまでも鉈の音は続いている。手伝えばよいのにその気がない息子。
■松井洋子 選
薄氷に風の記憶と夜の記憶 雅子
立春の護符のはみ出す回覧板 栄子
針供養男はカメラ持つばかり 一枝
包装紙きれいに畳み春隣 栄子
☆耕運機相模の山の忘れ雪 敦丸
大きな景の力強い句。目の前の耕運機は、眠っていた黒い土を起こしながら大きな音を立てて進む。
その背景の山々にはまだ斑雪も見られ、風も冷たい。しかしすでに春は動き出している。
■長谷川 一枝 選
いぬふぐりあの日の海の色したる 優美子
耕運機相模の山の忘れ雪 敦丸
春寒し被爆の使徒の身動がず 洋子
枝打ちの母の鉈音日脚伸ぶ 優美子
☆定小屋の礎石白梅散りそむる 洋子
定小屋の礎石でひとつの光景が思い起こされました。旧き良き時代行事のあるたびに掛っていた芝居小屋。それがいつ頃からだろうか忘れ去られてしまった。ただ傍らの白梅は変わらず咲き、そして散り始めた。
■山内 雪 選
温泉の湯気迷ひつつ春空へ 味千代
春の星ふつと田舎にゐるやうな 宏実
猫に餌やるなと春の神の宮 雅子
春昼や無音テレビの診療所 道子
☆追ひかけてゐるのはどつち春の野に 紳介
春の野のおおらかさが感じられる。
■辻 敦丸 選
指さしてこれは椿と子に教へ 一枝
菜の花や雨の予報の誤たず 康夫
立春の護符のはみ出す回覧板 栄子
餺飥を囲み話題は春一番 味千代
☆息抜きが本気になりて春の宵 一枝
忙しい日々、一寸息抜きにと始めた事が面白くなり時を忘れて、こんな事ありました。
■中村道子 選
どこからか校歌流るる春野かな 紳介
ブロンズの麒麟の背に春の雲 洋子
春立つや万葉集の相聞歌 一枝
都会へのあこがれ少し受験生 雅子
☆いぬふぐりあの日の海の色したる 優美子
今、あちこちに犬ふぐりの花がたくさん咲いている。日の光によって薄くも濃くも見える犬ふぐりの花。作者にとって多分特別な「あの日の海の色」はどんな色だったのだろうと想像しました。
多分瑠璃色に輝く美しい海の色……。
■黒木康仁 選
耕運機相模の山の忘れ雪 敦丸
陽の光薔薇の新芽の開く音 範子
嘴の濡れてきらきら水温む すみ江
春浅し優しい嘘もやはり嘘 味千代
✩春一番物干し竿の落つる音 道子
昭和のなごやかな風景が見えるようです 。
■千明朋代 選
とりあへず明日は生きむ春の星 優美子
梅の蕊びびびびびびと風の中 康夫
絶望も希望もなくて寒オリオン 優美子
花びらの濃淡梅の散り敷ける 雅子
☆春浅き川に佇む鷺の影 道子
私も鷺の立っている姿を句にしたいと思っているのですが、この句は情景が見えるようで感心しました。
■森山栄子 選
その色も被り心地も春帽子 田鶴
日日に目薬さして寒の明け 康夫
春の夜の心して書く手紙かな 道子
迸ること楽しくて春の川 雅子
☆薄氷に風の記憶と夜の記憶 雅子
一読、絵本のようだと思った。薄氷の表面の風紋や不透明さは、一夜の出来事のあらわれであり、形を結ぶまでに映した景色をも想像させる一句。
■チボーしづ香 選
温泉の湯気迷ひつつ春空へ 味千代
針供養男はカメラ持つばかり 一枝
正客問ひ亭主戸惑ふ春茶会 朋代
香りたち隠せぬ我の桜餅 宏実
☆指さしてこれは椿と子に教へ 一枝
親子の温かい心の感触と春ののどかさがシンプルに表現されているのがとても良いと思います。
■田中優美子 選
水鳥のほどよき距離を保ちけり 栄子
立春の護符のはみ出す回覧板 栄子
包装紙きれいに畳み春隣 栄子
春浅し優しい嘘もやはり嘘 味千代
☆ある朝の北半球の春野かな 紳介
「北半球」という大きな視点が面白い。春が訪れ、穏やかな野の風景が望めるのも、地球が回り、季節の巡りがあってこそのこと。当たり前すぎて普段は意識しないが、それ自体が奇跡的なことだと気づかされる。
■深澤範子 選
冴返る遺族年金申請書 優美子
春浅し優しい嘘もやはり嘘 味千代
いぬふぐりあの日の海の色したる 優美子
春昼のバス一人乗り二人降り 田鶴
☆その色も被り心地も春帽子 田鶴
きっとパステルカラーの春らしい素敵な帽子なのでしょう。とてもお似合いで気に入っているご様子。
春が近づいてきて、うきうきした感情が伝わってきます。
■長坂 宏実 選
ふきのたう初物香る句会かな 範子
バレンタイン無くなれ義理のチョコ包み 雅子
春寒や誰にも会はぬ散歩道 道子
春一番物干し竿の落つる音 道子
☆昔日を犬も偲ぶか夜の梅 康仁
ずっと寄り添っていたであろう愛犬と一緒に夜の梅を、静かに眺めている様子が伝わってきます。
■山田紳介 選
蝋梅山茱萸三椏女神統ぶ 朋代
春の夜の心して書く手紙かな 道子
包装紙きれいに畳み春隣 栄子
曖昧がよけれ人の世かぎろへる 朋代
☆遠つ国の歌なつかしき春の鳥 雅子
行ったことのない遥か遠く国の歌、聞くだけで故郷の懐かしい顔が浮んで来る。
歌に託された思いに国境はない。「春の鳥」が効果的。
◆今月のワンポイント
「季語は語る」
季語は単なる約束事や季節のシンボルではありません。文学上の奥行きと、共通の体験という幅を持つ凝縮された言葉です。
詠もうとした思いを託せる季語を吟味し、季語に雄弁に語ってもらいましょう。
西村和子著「添削で俳句入門」(NHK出版より)