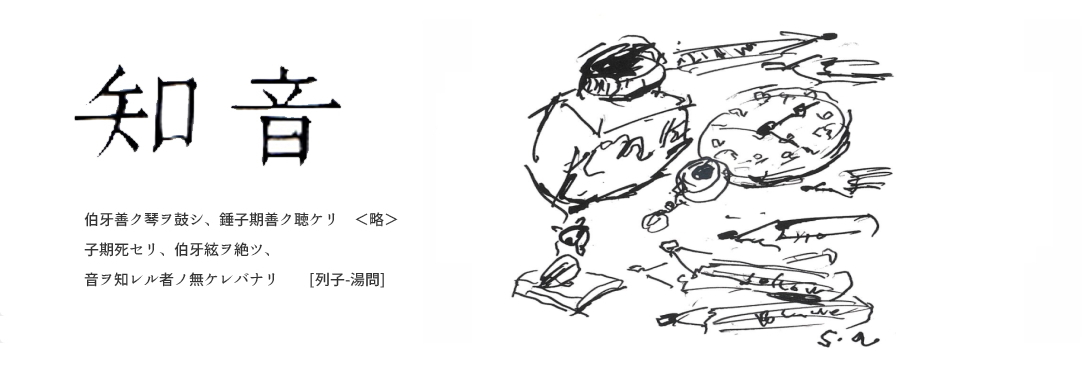西馬音内盆踊り 行方克巳
立てかけしごとをちの滝こちの滝
山清水くねりつつ行く葛の花
爪に火を点す浮世を踊りけり
やさしうてごつうて男踊りかな
きはめつき男踊りの女かな
帰るさの彦左頭巾をはね上げて
暗がりに踊り崩れの二三人
踊り笠たたみて立てば蹴転めく
真葛原 西村和子
真葛原一刀両断単線路
突兀と顕れ上州の霧の山
朝霧の香を部屋深く肺深く
霧飛ぶやヒマラヤ杉は翼垂れ
蹂躙を咎めず許さず螢草
おほかたの事は赦され夢二の忌
草々の露踏み分けて画室訪ふ
邯鄲や風のささめきさへ怖れ
不 眠 中川純一
八月の芝を突つ切り三塁打
盆花を選りつつ頼りなき視力
蟬しぐれ浴びつつ句碑の女文字
句碑の文字判じて腕の蚊を叩く
おやこんなところに萩とふれてみる
新涼の手ごたへ画布の空色に
嬉しさの不眠もありて明易し
水引草咲いて血圧正常値
◆窓下集- 10月号同人作品 - 中川 純一 選
探幽の龍と翔びゆく昼寝かな
佐瀬はま代
湯引きして一瞬鱧の花開く
黒木豊子
帯きゅつと締め炎天に立ちむかふ
小野雅子
膝折りてこの鈴蘭を賞でし日も
村地八千穂
狛犬の背ナに傾ぎて濃紫陽花
村松甲代
朝顔の大輪風に浮き上り
山田まや
仲見世の裏手に購ひし団扇かな
黒須洋野
見せる人無き黒髪を洗ひけり
松井洋子
浅草の雑踏にゐて青鬼灯
島田藤江
たまさかは夫婦気の合ひ冷奴
川口呼鐘
◆知音集- 10月号雑詠作品 - 西村和子 選
鉾建の縄屑もまた匂ひ立ち
米澤響子
化粧室涼しゲランの瓶の青
牧田ひとみ
海芋咲く町のどこにも水の音
吉田泰子
十薬をきれいに残し寺男
大橋有美子
新橋をポンヌフと呼び巴里祭
吉田林檎
夏雲やキッチンカーは翼持ち
志磨 泉
ざら紙のやうな思ひ出梅雨じめり
中野のはら
涼しさや石の館に木の調度
井出野浩貴
一滴のすでに大粒大夕立
磯貝由佳子
遺失届書く首筋に額に汗
井戸ちゃわん
◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子
しんがりの大船鉾のもう見えず
米澤響子
祇園祭の後祭のしんがりである。京都の祇園祭は元来前祭と後祭の二回に分けて巡行が行われていたらしいが、このところ七月十七日に全ての山と鉾が巡行を行っていた。数年前に元の形に戻そうというので、後祭の巡行が復活した。私も久しぶりに後祭の巡行を見に行ったが、最後に登場する大船鉾の堂々たる歩みは感動的だった。
この句は「もう見えず」と言っていながら、祇園祭の全ての巡行の様子が眼裏に蘇ってくる。特に今年は三年ぶりに実施された巡行を、京都の人々はもちろん、全国の人々が心待ちにしていた。無事に巡行が終わったのを目の当たりにして、もう見えなくなった大船鉾の名残を惜しんでいる。
小児科の二階に眼科花うばら
𠮷田泰子
町医者の情景だろう。父親か母親が小児科医院を開業し、その二階に息子か娘が眼科を担当しているのだろう。大病院でないことを語っているのは「花うばら」の季語である。なんでもない郊外の光景だが、一読住宅街の個人医院だなということがわかる。そこが名医だとか、自分の世話になっているというわけではなく、見かけたままを詠んだ俳句。こんなことは俳句でなければ作品にはならないだろう。
春寒し対話の顔に口のなく
大橋有美子
疫病の流行で人と会うときはマスクを掛ける習慣が身について三年目となる。本来冬の季語であるマスクが無季のもののように詠まれ始めて久しい。この句は「マスク」という季語は使わず、そんな疫病禍の暮らしぶりと心情を詠んだもの。
対話するとき、目を見て声が聞こえれば不自由はなさそうに思えるが、口元の表情が見えないということは、考えてみれば心許ないものだ。同じ言葉でも、微笑みながら話しているのか、口を皮肉そうに曲げながら話しているのかわからない。その寒々しい心境を託しているのが季語である。