制服の皺彼らしく卒業す
大塚次郎
「知音」2024年6月号 知音集 より
客観写生にそれぞれの個性を
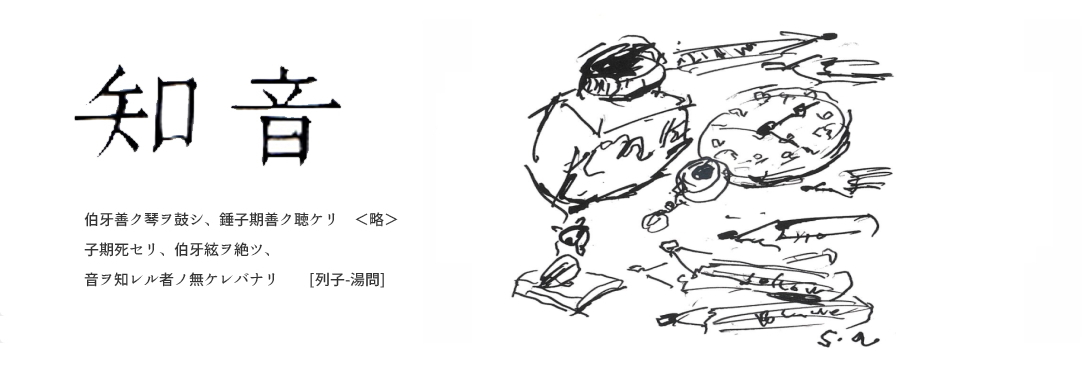
「知音」2024年6月号 知音集 より
亡き母と同じことして年用意
千明朋代
「積極的に伝統を受け継いでゆく」のではなく、「気がついたら、そうなっていた」という小さな気づきを発見し、一句に仕立てあげられました。そこに俳句の味わいが感じられます。
ことさら吟行に出かけなくても、丁寧な日常を送っていると、句材や句想は自ずから湧いてくるものだと、改めて考えさせられました。(中田無麓)
寒戻る木造家屋築百年
水田和代
一句を読んで想像が直ちに立ち上がってきます。明治期の建築の堅牢な柱や梁、それらに囲まれた静謐な空間の佇まいが凛としていて、季題に相応しい空気感を醸し出しています。
韻律の面で特徴的なのが、「戻る」を除いたすべての語が、音読みになっていることです。その硬質な音感も季感に花を添えています。(中田無麓)
和布刈神事火の粉激しく渦を巻き
木邑杏
行事や観光地をエトランゼとして詠む際、ある種の句は「絵葉書俳句」と揶揄されることがあります。では、「絵葉書俳句」とは何でしょうか? 個人的には、その地、その行事の持つ既成概念や既成イメージから抜けきれない句、あるいは一句に情報を過多に詰め込んだ俳句かと思います。
作者がエトランゼか否かはさておき、掲句には「絵葉書俳句」の要素が見当たりません。その大きな理由の一つが、「自身の心が最も揺り動かされた点」に絞って、潔く詠み下していることにあると言えます。神事を取り巻くいくつもの情報、例えば厳寒、桶、神職の装束などには触れず、松明から舞い上がる火の粉のみに焦点を当てたことが鮮やかな印象につながり、凡百の説明を超えた訴求力になっているのです。(中田無麓)
結論のでるまで歩く枯野原
片山佐和子
「枯野」という季題の本意を、物理と心理の両面から鮮やかに切り取られた一句と言えましょう。結論の出ないうちは荒涼たる野面であるという把握は、即物的に描きながらも、心象をも大いに発露されています。仮に下五を大花野や芒原に置き換えたとしましょう。同じ5音でも、枯野原以外の季語の斡旋は考えられません。
今は孤愁の只中にいる作者ではありますが、結論が出さえすれば、植物の命は、草萌や芽吹きに向かいます。そんな希望も掲句からは読み取ることができます。(中田無麓)
朱鷺色に筑波嶺染まる初茜
穐吉洋子
大景が正面から悠揚迫らず描かれていて、気持ちの良い一句になりました。関東平野のそこかしこから望める独立峰の筑波山。横山大観の富士山絵のような趣きがあります。
加えて、掲句で注目したいのは、微妙な色彩の饗宴です。朱鷺色の峰の色と、稜線を隔てた茜色。とても繊細な日本の伝統色のアンサンブルが洗練されています。「紫峰」という筑波山の別名を知っていてもいなくても、名峰の形容に相応しい描出と言えるでしょう。(中田無麓)
堆き上に絵馬掛け初詣
五十嵐夏美
掲げられる絵馬の願いで多いのは、恋愛成就や合格祈願が通り相場です。京都の北野天満宮などが代表的でしょう。その絵馬が「堆く」奉納されているというのですから、その数は半端ではありません。
この「堆い」という形容詞の斡旋が掲句の大きなポイントになっています。語意は「もりあがって高い(広辞苑)」こと。つまり体積と量感にリアルな存在感があるのです。因みに上五を「数多き」や「嵩高き」に言い換えてみると、言葉の選択の的確さがわかると思います。
一句はモノに即して客観的な写生に徹しているのですが、読み手はただただ、祈りの熱量に圧倒されるばかりです。(中田無麓)
福笹をおしいただきて爺破顔
小野雅子
場面転換が鮮やかな一句です。上五中七に宿るのは厳粛な気分と敬虔な気持ち。言わば「静」の世界です。一方、下五はそこから一転して破顔という「動」の世界に移ります。静と動、聖と俗の同居が十日戎の特徴です。掲句は僅か17音の中に、行事の本質が鮮やかに詠み込まれています。「破顔」という言葉の中に関西人の十日戎への思いも色濃く滲み出ています。(中田無麓)
着ぶくれて自転車から転がりさう
石橋一帆
「着ぶくれ」という季題は、どちらかと言えば自虐気味でネガティブな心象の表象として用いられることが多いのですが、掲句はズバリ実景に即した物理的な印象を与えていてユニークです。オジサンかオバサンか? どんな自転車か? 用事か遊びか? 読み手の想像力を掻き立ててくれる面白い句でもあります。
とは言え、ただ面白いだけではなく、本気で心配している作者の心情も、言外に伝わってきます。このやさしさが救いになっています。中七から下五にかけての句またがりの不安定感がかえって功を奏し、不安や心配を増幅させていて巧みです。(中田無麓)
たちまちに雪呼ぶ雲となりにけり
片山佐和子
同様の空模様を指す季題に「雪催」がありますが、その静的なイメージとは裏腹に掲句は、スピード感を伴った動的な句姿が印象的です。にわかにかき曇った空の変容の速さと、その後の長い静寂が対比的に描かれているのもポイントです。「たちまち」で速さを、「なりにけり」で静寂の継続を、という使い分けも巧みです。
季題はそれ自体、洗練されながらも多くの含みを持つ、磨き抜かれた言葉ですが、ときには季題を「因数分解」することで、新しいイメージを獲得することもできます。(中田無麓)
寒鰤や怒濤といふは心にも
小野雅子
「寒鰤」という季題が極めて効果的に用いられています。読み手は冬の日本海沿岸の漁港、あるいはその周辺の漁師町や海岸で荒れた海を見ていることが想像できるのです。
それ以上に掲句の味わいは、心の中に荒ぶる怒涛を発見したことにあります。「心」を使った句は、写生から離れて一人よがりになりがちですが、一句の表現は抑制が効いていて、しかも写生から隔たることはありません。下五の「にも」という助詞の連語から、眼前の景と心象との並列であることで明らかです。心中の怒涛の訳は明らかではありませんが、実景の怒涛の激しさを描写する術としても巧みです。(中田無麓)
福笹を大魚のやうに掲げ来る
小野雅子
大魚という比喩が秀逸です。おそらく吉兆が鈴生りで、その重みにより福笹も撓みに撓んでいることでしょう。えべっさんの鯛からの連想も隠し味になっているようです。京都の宮川戎、大阪の今宮戎、兵庫の西宮戎など、人出の多い十日戎の景かと拝察しました。
掲句は簡単に見えて、実に奥行の深い句でもあります。句中の大魚は実際に得た実利ですが、大魚のように掲げる福笹やその飾り物である吉兆は願望や祈りと言った虚にすぎません。商売繁盛という実利が得られるかどうかは、定かでありません。言わば、反故になるかもしれない約束手形のようなものです。それにも関わらず、すでに約束されたものと疑わず、晴々と堂々と闊歩するというのです。ここに関西人ならではの気質やえべっさんへの信頼の深さが垣間見えます。(中田無麓)
山の音ごろりごろりと北颪
辻敦丸
「山の音」と言えば、地鳴りや風音と言った自然の音を指しますが、川端文学の題名を連想するケースが、大方の向きのようです。掲句も人間の暗い部分、不安や焦燥といった要素が多分に含まれていて、小説としての「山の音」を踏まえた作りになっていると勝手に想像しました。その所以は中七の「ごろりごろり」という擬音語。重厚ながら角張った語感、少し耳障りな響きが不気味であり、得体のしれない魑魅魍魎を思い起こさせます。
一方、川端を下敷きにしなくても、一句は充分な量感をもって成立します。モノトーンを背景に自然への畏怖が描き切れているのです。(中田無麓)
豚汁の味見をしつつ春を待つ
松井伸子
枝先の紅烟る梅蕾
水田和代
寒紅をさして一日の力とす
(寒紅をさして一日の力かな)
片山佐和子
年詰まる報道局の喫茶室
宮内百花
知らぬ間に声きつくなる小晦日
千明朋代
買初のおまもり緋色みどり色
三好康夫
朝日受け篝火草の一段と
鎌田由布子
熱々の鯛焼を待つ列無言
板垣もと子
花びら餅一人のための薄茶たて
小野雅子
雪白の富士にちからを貰ひけり
松井伸子
トロ箱の鮟鱇どろり目鼻口
木邑杏
空っ風もじゃらくじゃらの髪になり
辻本喜代志
閉店の知らせまたもや年の暮
宮内百花
笑ひては泣いては笑ひ初芝居
板垣もと子
冬の空うす紫に暮れゆけり
若狭いま子
一人欠け女正月集ひけり
箱守田鶴
サッカーの子らの声聞く散歩かな
平田恵美子
大寒や靴音硬き石畳
若狭いま子
春近し宵の明星雲を抜け
鏡味味千代
日射しある方へ方へと梅探る
佐藤清子
電車バス乗り継ぐ子らや冬うらら
宮内百花
冬の雲街はくもりて海光る
平田恵美子
鎌倉の路地より女礼者かな
奥田眞二
飛行機が窓を横切り風邪心地
(飛行機は窓を横切り風邪心地)
鏡味味千代
寒卵ですよと女将愛想よき
(寒卵ですよと愛想よき女将)
奥田眞二
庭先の沈丁蕾固きまま
水田和代
春隣烏ふはりと舞ひ下りぬ
松井洋子
土塊のやうな牡蠣蒸す一斗缶
(一斗缶で蒸す土塊のやうな牡蠣)
森山栄子
筑波山二峰くっきり寒の朝
穐吉洋子
白きもの眉にも見つけ初鏡
(白きもの眉にも有りぬ初鏡)
穐吉洋子
寒晴や楠公像の馬猛り
森山栄子
悉くすれ違ふ人息白く
深澤範子
元気かと添へて名無しの年賀状
松井伸子
藍染の冬のエプロン身になじみ
若狭いま子
寒の雨千年の楠煌ける
木邑杏
恋歌と解る年ごろ歌留多読む
佐藤清子
日当たりの良きところより水仙花
水田和代
冬晴やをさな子の絵に迷ひなく
松井伸子
推敲の一句の如何に初句会
(推敲の一句如何にや初句会)
奥田眞二
寒雷や潮鳴りに沿ふ五能線
小野雅子
鮪の頭どんと据ゑあり魚の棚
平田恵美子
行き先は未定の一日小六月
千明朋代
野の果ての讃岐山脈雪積もる
三好康夫
「知音」2024年6月号 知音集 より
「知音」2024年6月号 知音集 より
「知音」2024年6月号 知音集 より
「知音」2024年6月号 知音集 より
「知音」2024年5月号 知音集 より
「知音」2024年6月号 知音集 より
「知音」2024年6月号 窓下集 より
「知音」2024年6月号 知音集 より