風はらみ風にまくられ春ショール
白岩静江
「知音」2024年7月号 知音集 より
客観写生にそれぞれの個性を
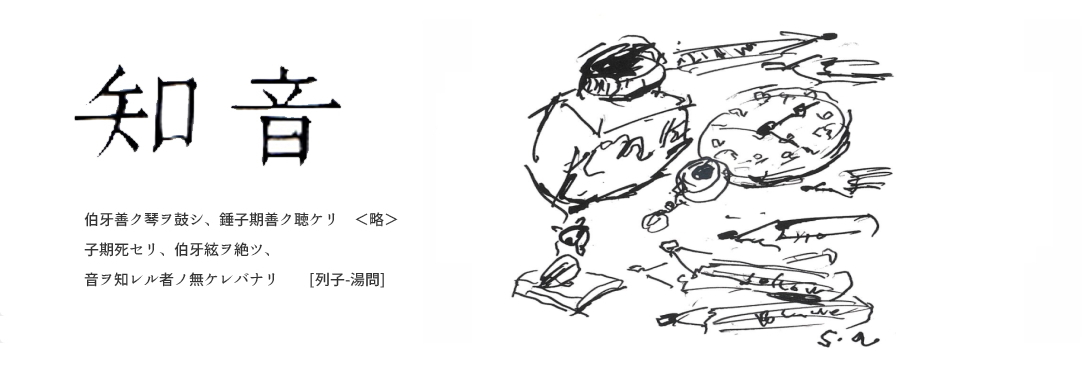
「知音」2024年7月号 知音集 より
「知音」2024年7月号 知音集 より
「知音」2024年7月号 知音集 より
「知音」2024年7月号 窓下集 より
「知音」2024年7月号 窓下集 より
「知音」2024年7月号 窓下集 より
「知音」2024年7月号 窓下集 より
「知音」2024年7月号 窓下集 より
「知音」2024年7月号 窓下集 より
底冷や百間廊下磨きたて
百間廊下寒行僧の素手素足
寒行の声百間を貫きぬ
寒行や心の迷ひ筆に出て
来たるべき喜寿の諸手に破魔矢受く
押し切れば歯軋り返す冬菜かな
潜みゐし時は何色龍の玉
密なるを以つてよしとす龍の玉
竹馬の王子よ地球乗りこなし
繭玉や飲み食ひ笑ひかつ怒鳴り
冬桜この日この時違ふなく
道行の菰を傾げて冬牡丹
頽齢といふ一ト盛り冬牡丹
石垣のやうに崩れて大浅蜊
ぐるつくぐるつく鳩どちバレンタインの日
剃刀の捨刃匂へる余寒かな
年酒酌む杜氏の妻を描きし絵と
人日や原稿書きもひと区切り
松過ぎの隘路に資源回収車
どてらよりぬつと握手の腕伸ばす
どてら着て農家の嫁が板につき
純白の母の水仙咲きにけり
水仙や何かと鳩の寄つて来る
物の芽のシンデレラたるそのひとつ
クリスマスソング仄かに昇降機
中津麻美
長き夜の悲恋小説飽き飽きす
田中優美子
海を恋ふ退役船へ木の葉雨
牧田ひとみ
萩刈られ風の見えざる庭となり
山田まや
丹の橋に小紋ちらしの落葉かな
吉田しづ子
外套の長き抱擁始発駅
川口呼瞳
暖炉の灯見つめる背の人寄せず
大橋有美子
物置の鍵穴錆びし枇杷の花
野垣三千代
腕振れば歩幅広がり冬青空
辰巳淑子
星冴ゆる咫尺に月の弓を立て
上野文子
冬晴やヘリコプターの音近し
松枝真理子
子育てに失敗葱が食へぬとは
井出野浩貴
落葉投げ上げ誕生日おめでたう
田中久美子
日の丸は単純明快冬青空
くにしちあき
なにがしの館趾より秋の声
藤田銀子
日向ぼこ猫は耳から振り向きぬ
吉田林檎
鵙の声届き電波の乱れたる
立川六珈
茶の花のほつほつと咲きぽろと散り
中野のはら
空耳にあらずたしかに残る虫
山田まや
冬青空対岸に雲押さへつけ
大橋有美子
下五を逆接で言いさしていることから、大学の名は変わっても、キャンパスの晩秋の光景は昔と変わらない、と言いたいのだろう。東京工業大学が東京科学大学に、大阪外大が大阪大学外国語学部と変わったように、世の中の変遷や大学の経営の都合で、名前が変わることはよくあることだ。この句に詠まれている大学は、歴史があって銀杏並木が立派なのだろう。そこに愛着を感じている作者なのだ。
大阪の御堂筋は、最大八車線、幅四十四メートルの大通りで、戦争中万が一の時は飛行機の離着陸ができるように道幅を広げたと聞く。そこを通り抜ける風の速さを、「ビル風を秋風が追ふ」と表現した点がポイント。今は両側にビルが立ち並んでいるが、もともとは大阪の商家だった。
私が関西に移り住んだ頃、大阪は無断駐車が多かったが、もとはうちの敷地だったという思いが影響していたと聞いたものだ。ビルの前に、二重三重に無断駐車する現象は珍しくなかったものだが。
十三夜水の面もくもりなく
山田 まや
この句のポイントは「も」にある。言うまでもなく、十三夜の月の出ている空は澄み渡っている。仲秋の名月よりも遅い時期なので、空気はより冷やかになり、月光も曇りない。その月が映っている水の面を描写して、空の光景を想像させるという心憎い手法を取っている。