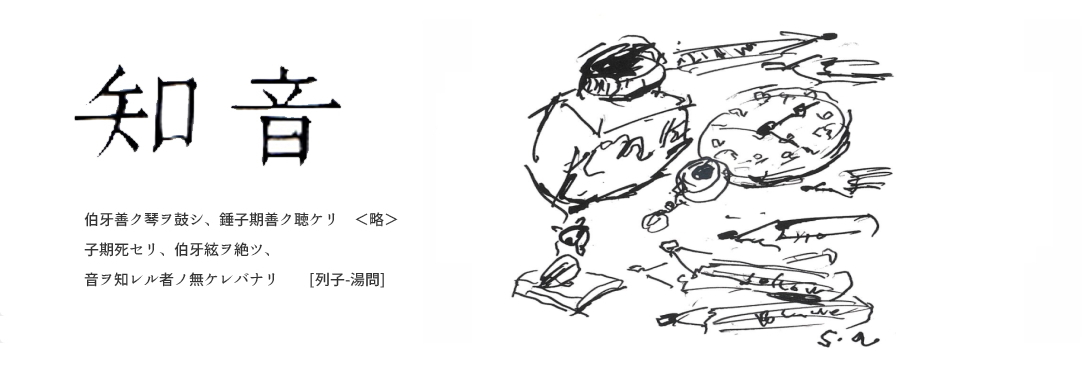独り言 行方克巳
浅春の用なき十指もみほぐす
淺春の何やら路地の人集り
晩年や十薬干して芹つんで
踏んごみてすぐに清らや芹の水
急ぐごと急がざるごと蜆舟
喪心のかそかなりけり蜆汁
独り言噛んでしまへり冴返る
春は名のみの名もなきひとよよかりけり
ブロンズ 西村和子
春夕焼全面玻璃の美術館
春灯が生むブロンズの影不思議
朧夜のシーソーイヴに傾きぬ
存在はあやふし春はさだめなし
花便り聞かむ京より夜の電話
さしのべし枝より兆す桜かな
初桜ひと夜ひと日に咲きふゆる
暮れ残る一隅雨の利休梅
美術館 中川純一
春暁や起き出て仰ぐエトナ山
春寒の袖を滑つて出でし腕
ミモザの花束ねて思ひだし笑ひ
春寒や砥石濡らせば手も濡れて
長閑しや何話しても笑ふ嬰
春光や十時にひらく美術館
はやばやと弁当済ませ蓬餅
鈴蘭や北大教授眼が優し
◆窓下集- 5月号同人作品 - 中川 純一 選
一山の万の臘梅墓一基
佐瀬はま代
餓鬼のごと豆を欲りたる鬼やらひ
小倉京佳
小指の先ほどのさびしさ春を待つ
山田まや
酒止めし夫の秘蔵の年酒受く
井戸ちゃわん
春着縫ふ母は正座をくづさざる
田代重光
一月の書店樹木の匂ひせり
中津麻美
登校のランドセルより春の音
牧田ひとみ
風呂敷に羊羹二棹春寒し
廣岡あかね
我が道はどこまで続く冬北斗
深澤範子
楠に燃え移りさうどんど焼
岡本尚子
◆知音集- 5月号雑詠作品 - 西村和子 選
大川に波のなき日や納め句座
磯貝由佳子
裸木に常盤木に風光りけり
井出野浩貴
居どころのないのか日向ぼこなのか
藤田銀子
探梅や扇ヶ谷を行きもどり
前山真理
初電車救護服着て被災地へ
三石知左子
箱のやうな家建ち並び春隣
松井洋子
街師走うつむく我を置き去りに
立川六珈
山国の午前十時の初日の出
金子笑子
春宵の人形遣ひ腰反らし
牧田ひとみ
寒牡丹己が美しさを知らず
松枝真理子
◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子
葱刻む薬飲むほどでもなき日
磯貝由佳子
作者は体調が悪く薬を常用しているのだろう。しかしそれは毎日というわけではなく、不調ではあるが薬を飲むほどではない日という一日を詠んだもの。
今日は薬を飲まなくても大丈夫そうだと思った日に、外出するとか遊びに行くというのではなく「葱刻む」という地道な家事に専念した、という点に注目した。葱を刻むのは、いうまでもなく家族のための家事の象徴。同時発表の〈葱たんと入れて武州の太うどん〉のように、味覚に訴えてくる句はおいしそうでなければ意味がない。「たんと」に含まれるニュアンスは、常々「たんとおあがり」と言って子供を育てたおかあさんならではの言葉の選び方だと思う。
薄氷を掬へば水の動きそめ
松井洋子
「氷」は冬の季語だが、「薄氷」は春の季語であることを念頭において味わうと、この句の水の動きが春の息吹と感じられてくる。子供の頃薄氷を割らないように掬い上げることを誰もがした覚えがあるだろう。そんな童心に帰って薄氷を剥がしてみたら、水がほのかに動きはじめた。その瞬間を描いた、春のはじめの句。
山国の午前十時の初日の出
金子笑子
作者は老神温泉の老舗旅館の女将。知音の仲間も毎年のようにお世話になったものだ。この句を読んで、「伍楼閣」の部屋から見た朝日を思い出した。温泉郷の東に屏風のように立ちはだかっている山々に朝日が昇るのは、かなり遅い時間だった。
初日の出が午前十時とは山国ならではの光景だ。非常に単純明快な一句だが、かなり特殊な地形を思い浮かべて鑑賞してほしい。