そよりともせぬ真夜中の新樹かな
井戸ちゃわん
「知音」2017年9月号 窓下集 より
客観写生にそれぞれの個性を
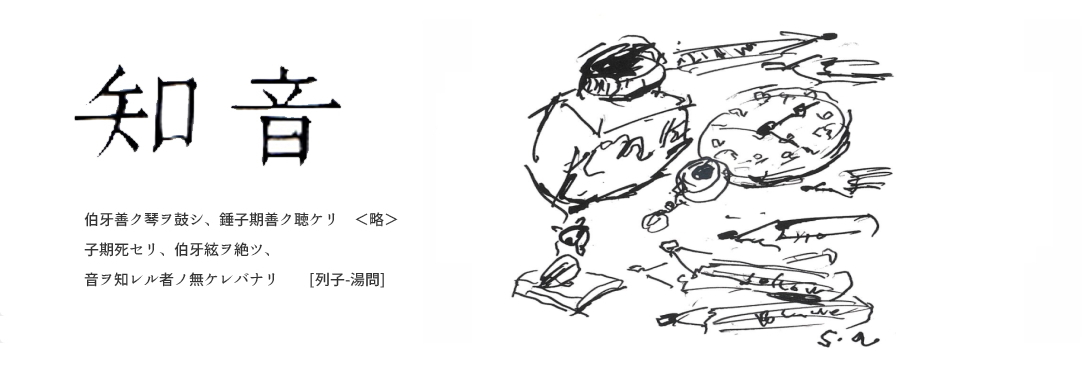
「知音」2017年9月号 窓下集 より
「知音」2017年9月号 窓下集 より
「知音」2017年9月号 窓下集 より
「知音」2017年9月号 窓下集 より
「知音」2017年9月号 窓下集 より
「知音」2017年9月号 窓下集 より
『句集 無言劇』 東京美術 1984刊 より
『句集 系譜』 角川書店 1985刊 より
休校の子らを誘ひて蓬摘
森山栄子
【講評】新型コロナ蔓延防止のため、春休みを待たずに休校になった。数日ならば嬉しい休みも、だんだん退屈になり体を持て余してくる。兄弟喧嘩も始まる。自分の子供だけではない。親が働いている子もいる。そんな子供達をなんとかしてあげたいと思いついたのが蓬摘み。近くの土手や原っぱの蓬は今がちょうど摘みごろ。日差しも風も気持ちよく、喧嘩することも忘れてせっせと摘んでいる子供達の様子も、手の中の蓬の香りも伝わってくる。帰ってから作る草餅も、この春の思い出の一つとなることだろう。(高橋桃衣)
春雨の色眠たげの東山
辻 敦丸
【講評】「春雨」は3月から4月にしとしと降り続く雨で、春の艶やかな情緒を感じさせる季語である。この句は「眠たげ」という言葉で、春雨の降りかたも、ぼんやりと見える東山の趣も描くことに成功しているが、さらに春雨の「色」と言ったことで、水彩絵具を溶いたような、柔らかく淡い彩りを読者に感じさせてくれる。
「春雨」はまた、木々の芽吹きを助け、花を開かせる雨でもある。京都の町並も、辻から眺める東山も、この雨に包まれて一段と春が深まっていくようだ。(高橋桃衣)
草餅や湯呑に郷土力士の名
森山栄子
【講評】 鶯餅、椿餅、桜餅などに比べて草餅は、手作りの温かみある素朴な餅である。お茶も、薄手で小ぶりな煎茶茶碗より、厚手で寸胴な湯呑がぴったりだ。しかもこの土地で皆が応援している力士の名が入った湯呑である。近くで摘んで搗いた蓬餅は色も香りもよく柔らかく、両手で包み持つ湯呑はあたたかい。視覚、嗅覚、触覚で、住む地への愛情を表現した句である。(高橋桃衣)
朝桜昨日と違ふ道選び
田中優美子
【講評】開花を待ち望み、咲けば風雨に落ち着かず、散り急ぐことを惜しみ、私たちの心を捉えて放さない桜。初桜から遅桜、葉桜になるまで、また1日の中でも朝桜、夕桜、夜桜、とそれぞれの風情を愛でて飽きない桜である。その中で、朝桜は明るく、新しく、1日の始まりに生きる力を与えてくれる。出勤の途中に出会うだけでも心が弾んでくる。
「昨日と違う道」は、桜が見たくていつもと違う道を選んだ、というだけではない。朝桜から元気と希望と勇気をもらった作者は、昨日を引きずることなく、今日という新しい一日に挑もうとしているのである。(高橋桃衣)
強東風やしつかと根付きスカイツリー
箱守田鶴
【講評】完成前には東日本大震災があり、634メートルという高さを不安がられたスカイツリー。いつの間にかそんな心配も忘れられ、すっかり東京の景色の一つになりきっている。
世界中で塔はタワーで、ツリーという名称のものはないというが、スカイツリーは天へ向かっていく木である。だからこそ植えて8年経ち、強風にもどっしりと構えている姿に、「根付き」という言葉が出たのだ。しかもこの風が台風ならば、じっと耐えているだけだが、強風でも「東風」である。風の向こうには明るい未来、希望がある。(高橋桃衣)
( )内は原句
最北の原野つらぬく雪解道
山内雪
伊那谷の花悠々と湛へたり
鏡味味千代
春の日やファンデーションを変へてみる
深澤範子
夜の潮静かに満ちて春の旅
山田紳介
かんばせのうすがみはがし雛飾る
長谷川一枝
空に溶けみづうみに溶け春の山
小野雅子
どの児より担任が泣き卒園式
松井洋子
春の灯の終の一つとなりにけり
山田紳介
雛飾るあの頃のこと子に聞かせ
長谷川一枝
初桜今日は昨日と違ふ朝
田中優美子
なじみたる数珠つまぐりて堂の春
小野雅子
涅槃西風逆らひ流され飛ぶ一羽
箱守田鶴
境内のしじま畏み朝桜
田中優美子
春休み路地一面に線路描き
箱守田鶴
コンビニへチューハイ買ひに夕桜
田中優美子
堂縁に老尼の草履ふきのたう
小野雅子
ここからはアリスの国ぞ落椿
松井洋子
触れし手へつつつと雫雪柳
三好康夫
草餅屋土人形のおつとりと
森山栄子
朧月めがね橋より出て来たる
深澤範子
ふらここの揺るる公園昼の月
中村道子
春雨に頭濡らして鳥ちょんちょん
小野雅子
彼岸寺住職替はり猫をらず
箱守田鶴
優雅には遠く白鳥鳴き交はす
山内雪
花冷えや休館続く美術展
長谷川一枝
日常の貴きを知る春の風邪
長坂宏実
世話好きは母系の血筋チューリップ
島野紀子
壁紙の模様に飽きて春の風邪
鏡味味千代
鶯のここぞといふ時鳴きくれし
箱守田鶴
白木蓮の蕾ビロード花サテン
藤江すみ江
(白れんの蕾ビロード花サテン)
「白れん」は「白蓮(びゃくれん)」のことになりますので、「白木蓮」または「はくれん」と表記しましょう。
おほ空へらせん階段春の鳶
小野雅子
(おほ空のらせん階段春の鳶)
大空へ上って行くのですから、「へ」です。
忘却は時のはからひ涅槃西風
松井洋子
(忘却てふ時のはからひ涅槃西風)
ふらここを大海原へ漕ぎくれし
藤江すみ江
(ふらここを大海原へ漕ぎくれし日)
風の匂ひ雨の音にも三月来
深澤範子
(風の匂ひ雨の音色や三月来)
うたた寝の腕の痺るる春炬燵
中村道子
(うたた寝の痺るる腕や春炬燵)
ひらかんと枝垂桜の息とめし
千明朋代
(咲きなんと枝垂桜の息とめし)
舞ひ降りて何処に行きし春の雪
辻 敦丸
(舞ひ降りて何処にあるや春の雪)
踏み出さぬ人の背を押す桜まじ
鏡味味千代
(踏み出さぬ人の背中押す桜まじ)
地に触るる枝垂桜の枝の先
千明朋代
(地に至る枝垂桜の枝の先)
春風や剣玉の音小気味よき
藤江すみ江
(小気味好き剣玉の音春の風)
各人が選んだ五句のうち、一番の句(☆印)についてのコメントをいただいています。
■小野雅子 選
要締め雛の扇のおさまりぬ 洋子
コンビニへチューハイ買ひに夕桜 優美子
風光るぶるんと母の耕耘機 優美子
雉啼きてなほ薄明を引き留むる 康夫
☆最北の原野つらぬく雪解道 雪
北国の暮らしは厳しく、半年は雪との闘いに明け暮れる。春が兆すと道が溶け始める。
最北の原野、ここにも人の暮らしがある。
■三好康夫 選
世話好きは母系の血筋チューリップ 紀子
風花や古代史講座たけなはに 雪
古雛や埃ひとつもなき調度 洋子
壁紙の模様に飽きて春の風邪 味千代
☆なじみたる数珠つまぐりて堂の春 雅子
コロナウイルスのために不安な世の中、やっぱり、この安心は代えがたいものがある。
■藤江すみ江 選
どの児より担任が泣き卒園式 洋子
父の手の藁で束ぬるほうれん草 道子
堂縁に老尼の草履ふきのたう 雅子
蝶の昼猫は薄目をまた閉ぢて 雅子
☆触れし手へつつつと雫雪柳 康夫
雪柳のひと片を雫と表現したところが いいなと思いました 雪柳のあの軽い花びらの実感だと思いました。
■箱守田鶴 選
どの児より担任が泣き卒園式 洋子
母の言ふ通りに雛を飾りけり 紳介
草餅や湯呑に郷土力士の名 栄子
ランナーの集団春雨跳ね上げて 雅子
☆コンビニへチューハイ買ひに夕桜 優美子
我が家でも飲み物は各自調達してくる。彼らも夫々夕桜を見上げているだろう。
チューハイの缶をかかえ、こよなく日常の中にある愛すべき夕桜、こんな花見が大好きだ。
■中村道子 選
最北の原野つらぬく雪解道 雪
春眠や本に隠れて昼休み 宏実
しづかさや木肌にあそぶ春日影 すみ江
草餅や湯呑に郷土力士の名 栄子
☆春休み路地一面に線路描き 田鶴
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、外出の制限が続いた今年の春休み。
路地いっぱいに線路を描く子供の姿が浮かぶ。早く電車に乗って自由に出かけたい。私も…。
■長谷川一枝 選
世話好きは母系の血筋チューリップ 紀子
忘却は時のはからひ涅槃西風 洋子
休校の子らを誘ひて蓬摘 栄子
春休み路地一面に線路描き 田鶴
☆おほ空へらせん階段春の鳶 雅子
ピーヒョロローと気持ちよさげに鳴きながら碧空を悠々と転回する鳶。この昏迷した状況をふと忘れさせてくれました。
■森山栄子 選
牛飼の村に白鳥大鳴きす 雪
酢をきかすポテトサラダや山笑ふ 朋代
雛飾るあの頃のこと子に聞かせ 一枝
堂縁に老尼の草履ふきのたう 雅子
☆空に溶けみづうみに溶け春の山 雅子
大景がゆったりと詠まれ、穏やかな心持ちになる。山笑うと表される春の山容が、空に溶けていく一相のように感じられた。
■鏡味味千代 選
春山を我がものとして養蜂家 雅子
鳥雲に船影遅遅と南南東 敦丸
草餅や湯呑に郷土力士の名 栄子
報はるることなけれども初桜 優美子
☆雉啼きてなほ薄明を引き留むる 康夫
雉の尾の先に薄明があるかのような、一服の琳派の絵のような句だと思いました。
■チボーしづ香 選
参道に人足途切れ風光る 田鶴
落ちてなほ椿の色のあざやかに 一枝
風の匂ひ雨の音にも三月来 範子
蹠より寒戻りくる畳かな 洋子
☆夜の潮静かに満ちて春の旅 紳介
夜の静けさに春の旅を満喫する旅人の心がよく出ている。
■松井洋子 選
空に溶けみづうみに溶け春の山 雅子
風の匂ひ雨の音にも三月来 範子
春風や剣玉の音小気味よき すみ江
雉啼きてなほ薄明を引き留むる 康夫
☆春の川渡りきりたるチューバの音 味千代
高校生だろうか、チューバを練習している音が対岸から聞こえる。かなり肺活量が要ると思われるが、いつまでも一人で吹いている。春光を浴びて流れる川とチューバの音、若々しい力が感じられた。
■千明朋代 選
雉啼きてなほ薄明を引き留むる 康夫
ここからはアリスの国ぞ落椿 洋子
春の川渡りきりたるチューバの音 味千代
鶯のここぞといふ時鳴きくれし 田鶴
☆春雷や耳立てたまま猫眠り 雅子
猫の緊張したまま眠る様子が今の日本の惨状を現わしているように思いました。
■辻 敦丸 選
最北の原野つらぬく雪解道 雪
父の手の藁で束ぬるほうれん草 道子
雉啼きてなほ薄明を引き留むる 康夫
ふらここの揺るる公園昼の月 道子
☆蹠より寒戻りくる畳かな 洋子
大乗寺の広い畳は各別でした。遠い昔の思い出です。
■黒木康仁 選
春山を我がものとして養蜂家 雅子
ここからはアリスの国ぞ落椿 洋子
春休み路地一面に線路描き 田鶴
風光る初めて寄りし和菓子店 道子
☆蝶の昼猫は薄目をまた閉ぢて 雅子
のどかな春の昼の光景が目に浮かんできます。下五によって余韻が。
■島野紀子 選
春山を我がものとして養蜂家 雅子
鳥雲に船影遅遅と南南東 敦丸
牛飼の村に白鳥大鳴きす 雪
酌をする手のぎこちなく春袷 味千代
☆忘却は時のはからひ涅槃西風 洋子
認知症を近親者に持つ方か、このように思ってもらえるお年寄りは幸せだな、徳を積んでこられた若き頃だったんだろうなと背筋を正しました。
■田中優美子 選
鳥雲に船影遅遅と南南東 敦丸
忘却は時のはからひ涅槃西風 洋子
壁紙の模様に飽きて春の風邪 味千代
ひらかんと枝垂桜の息とめし 朋代
☆春雷や耳立てたまま猫眠り 雅子
犬は雷を怖がりますが、なるほど猫ならこんなこともあり得そうです。一瞬、本当かしらと疑いましたが、泰然自若、気ままな猫なら耳を立てたまま寝入っていそうです。
可愛らしい様子が目に浮かびました。
■深澤範子 選
どの児より担任が泣き卒園式 洋子
朝桜空の孤独へ寄り添へる 優美子
強東風やしつかと根付きスカイツリー 田鶴
落ちてなほ椿の色のあざやかに 一枝
☆検診の数値まづまづ夫の春 雅子
日頃の旦那さまの健康を気遣う様子がうかがわれる。検診の数値がまずまずだったとほっとした様子が伝わって来る。
■山田紳介 選
空に溶けみづうみに溶け春の山 雅子
父の手の藁で束ぬるほうれん草 道子
ここからはアリスの国ぞ落椿 洋子
納むるをはや話しつつ雛飾る 洋子
☆伯山の語れば春の闇深く 味千代
このアナーキーで、刃物のように鋭い伯山のパフォーマンスを聞いて、私も同じ様な感想を持ちました。
■長坂 宏実 選
花冷えや休館続く美術展 一枝
コンビニへチューハイ買ひに夕桜 優美子
蹠より寒戻りくる畳かな 洋子
壁紙の模様に飽きて春の風邪 味千代
☆水仙を揺らしバス停までダッシュ 栄子
少し暖かくなってきた頃の、すがすがしくて爽快な日の出来事かなあと思いました。
■山内雪 選
花冷えや休館続く美術展 一枝
風光るぶるんと母の耕耘機 優美子
蹠より寒戻りくる畳かな 洋子
ふらここの揺るる公園昼の月 道子
☆おほ空へらせん階段春の鳶 雅子
見えるはずのないらせん階段が一瞬見えました。
「季語が動く」と言われることがあります。これは季語を別のものに置き換えても、その句が成り立つということです。
「風花や古代史講座たけなはに」
は、実際に風花が舞ったので詠まれたのかもしれませんが、
「春風や古代史講座たけなはに」
とすることもできます。
季語の持っているイメージ、季節感がその句を力強く語ってくれる、そのような説得力のある季語を選びましょう。(高橋桃衣)
『句集 祭』 角川書店 2004刊 より