ふと辻に消えしは空也冬ざるる
中野のはら
「知音」2019年3月号 窓下集 より
客観写生にそれぞれの個性を
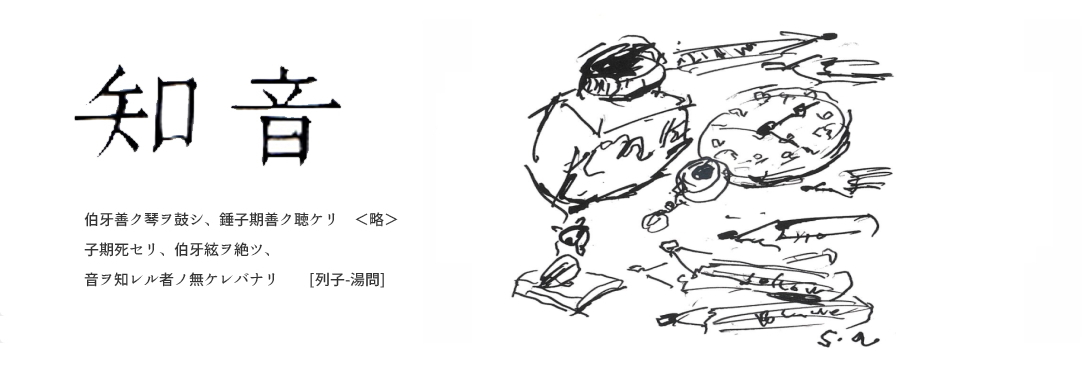
「知音」2019年3月号 窓下集 より
「知音」2018年4月号 窓下集 より
「知音」2018年4月号 知音集 より
「知音」2018年4月号 知音集 より
「知音」2018年4月号 知音集 より
「知音」2018年4月号 窓下集 より
「知音」2018年4月号 窓下集 より
「知音」2019年4月号 知音集 より
「知音」2018年4月号 窓下集 より
海桐の実弾けけふより膝栗毛
草の絮吹かれみちくさほどの旅
かの旅のみなかみ紀行しぐれ傘
牧水の気息の筆や冬あたたか
冬海やわれも眼のなき魚にして
露葎踏んで轍の行き止まり
寒禽の羽搏く光まみれかな
梓枯れ令和元年こともなし
裳裾まで新雪を刷き今朝の富士
打ち上げしものに根が生え冬の浜
風騒の人を散らしめ冬渚
詩のかけら拾ふ長身冬渚
散骨か流木か浜冬ざるる
松の影松に凭れて冬あたたか
冬草を敷きて流るる松の影
木と紙と竹の迷宮隙間風
曼珠沙華獣道にも飛び火かな
中川純一
ばらばらになるまで飛ばむ秋の蝶
米澤響子
ゆきあひの空の深さよ桃を捥ぐ
くにしちあき
えんまこほろぎおかめこほろぎ不眠症
井出野浩貴
わが句集わが手を離れ涼新た
吉田林檎
夢二忌の草食男子恋をせよ
藤田銀子
亡き人の句の偲ばるる桜蓼
江口井子
心あてに心まかせに秋の蝶
帶屋七緒
原つぱに遊ぶ子見えず秋の蝶
影山十二香
母を見し途端に破れ金魚掬ひ
植田とよき
爽やかや余白ばかりの山水図
田代重光
おそるおそるシャッター上げて野分あと
井内俊二
犬も子も蜻蛉集まる原つぱへ
松井秋尚
新涼や硬き背凭れここちよく
竹中和恵
小流れに木橋設へどんど焼
原 川雀
冷え冷えと光増したり今日の月
松原幸恵
朝顔を咲かせ空き家にあらざりし
井出野浩貴
秋澄めりその虹彩も雀斑も
中川純一
オール捌き苦手な男秋の風
小倉京佳
うらやましかりし栗の木ある家が
片桐啓之
駅頭などで日々さまざまなビラが配られる。そのほとんどは興味のないもので、人々はそっけなく無視して通り過ぎていく。たまたま作者はビラ配りの人と目が合ってしまった。そこに一種の共同の関係が生じて、貰いたくもないビラを受け取るハメになってしまったのである。そこには人間的なやさしさに通じるものがある。実はビラ配りのような何でもない仕事も大変なのである。誰も受け取ってくれなければ彼の役割は果たせない。残ったビラの束をごっそり捨てるわけにはいかないのだ。自分に取って役立ちそうにないビラでも受け取ってやればいい。どこかにそっと捨ててしまっても、ビラ配りの役割はそれで全うできるというものだ。そう、ティッシュが付いていなくても冷たく無視しないでそのビラ貰ってやりましょう。
野分の後の景である。様々なものが飛ばされて来ているのだが、これは一体何だろう。絡まり合うようにして飛んで来た何かが辺りに散乱しているのである。それを特定しなくても野分の去ったあとの雰囲気は充分感じ取れる。
ただ一匹鳴いている鈴虫の音色も美しいのだが、その鳴声が重なった時により一層の透明感を作者は感じ取ったのである。コーラスなどもその通りかもしれない。