そこにまた鹿の足跡木の根開く
高橋桃衣
「知音」2017年5月号 窓下集 より
客観写生にそれぞれの個性を
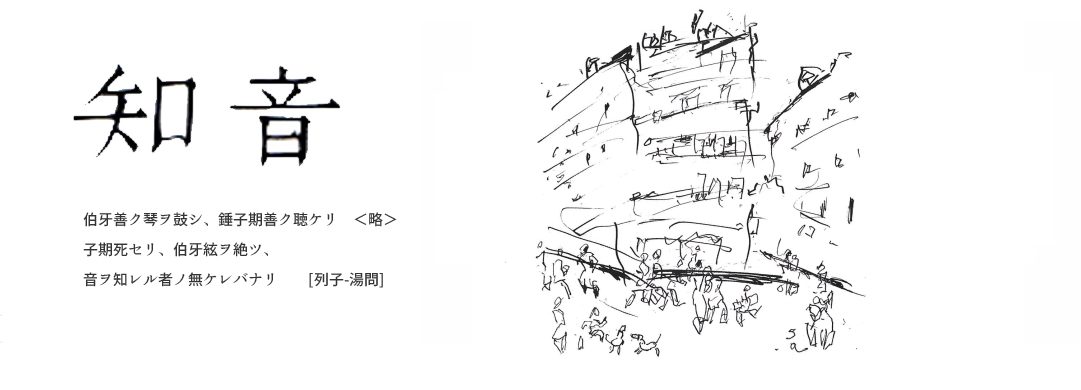
「知音」2017年5月号 窓下集 より
「知音」2017年5月号 窓下集 より
「知音」2017年5月号 窓下集 より
「知音」2017年5月号 窓下集 より
「知音」2019年5月号 知音集 より
「知音」2017年5月号 窓下集 より
探梅や見知らぬ人も句帳持ち
松井 洋子
【講評】「梅」「梅見」は春の季語だが、「探梅」は冬のうちに咲き出す梅を探して野山を歩くこと。冬枯れで寒々しい梅林を吟行していると、同じように梅を眺めながら歩いている人がいる。こんな時期に梅林を歩くのは俳人くらいだとよく見ると、案の定句帳を持っている。
作者は一人で吟行をしていたのだろう。俳句の仲間といたら見知らぬ人に気を止めることもないはずだ。そして話すでもなく共に梅に佇み俳句を案じるというささやかな縁に心通うものを覚えたのだ。(高橋桃衣)
探梅の尾根へぶつかる風硬し
松井 洋子
【講評】広々として起伏のある梅林は山へと続いている。寒風を遮るものは何もなく、尾根に衝突するかのように吹き抜けていく。「尾根」とあるので、連山が眼前に迫っているのだろう。荒涼としてまだ花も探すほどの梅林と、吹き曝しの広い空と、厳しい山の稜線を、「ぶつかる」「風」「硬し」と3回の「カ」で、荒い筆遣いの墨絵のように描き出している。(高橋桃衣)
トルソーのごとき白梅矍鑠と
黒木 康仁
【講評】トルソーとは彫刻の、顔や手足のない胴体だけのもの。本来はギリシャ彫刻などが時代を経て顔や手足を欠いたものだが、胴体だけでも充分に造形の美しさがあり、観る人を惹きつける。この古木の梅も枝をばっさりと伐られてはいるが、伐られたことなど気づいていないとばかりに、太い幹に元気に花をつけている。美しさも保っている。まさにトルソーである。春まだ寒い頃に開き出す白梅の気概をも見るようである。(高橋桃衣)
針先の触れし血の玉梅蕾む
三好 康夫
【講評】一般的に梅は、寒紅梅、白梅、紅梅の順に咲き出すと言われるが、実際の開花時期は種類や気候にもよる。また紅梅といっても真紅から薄桃色までまちまちであるが、学術的には枝や幹の断面が赤い色をしているのだそうだ。そう、この紅梅の幹には赤い血が通っていて、針が触れたのでたちまち小さな血の玉ができたのだ。
その血の玉は針の先が触れた程度である、と細やかに表現したことで、蕾の小ささ、枝にくっ付くように出ている様子が想像できる。また玉の表面張力と「蕾む」という動詞から、膨らもう、花を咲かせようという力が感じられる。
虚子の句の「紅梅の紅の通へる幹ならん」の「紅」は生命力というものを言っているのだが、それに通じるものを感じさせる句である。(高橋桃衣)
防犯灯ふいに点きたる寒さかな
森山 栄子
【講評】他人の敷地や家に入って行った時に防犯灯がついても、不意についたと驚くほどではないだろうから、暗くなって家に帰って来た時と考える方が順当だろう。
自分の家なのだから防犯灯があるのも知っているし、つくのもわかっている。それでも侵入者が来たかのように暗闇の中に浮かび上がらせてついた防犯灯に、人を信用しない冷え冷えとしたものを感じたのである。この「寒さ」は心の中の寒さでもある。(高橋桃衣)
( )内は原句
梅を見に光源氏の講義終へ
山内 雪
梅日和黄門さまに迎へられ
長谷川 一枝
老梅の精気前頭葉に受く
小野 雅子
閑谷にひびく朗唱梅の花
黒木 康仁
石段を登りきるなり梅の花
長坂 宏実
落葉松の影も写して雪光る
中村 道子
夜の雪かすかに匂ひあるやうな
山田 紳助
寄生木の葉の瑞々し降誕祭
小野 雅子
葬に集ふ婆みな似たり冬帽子
山内 雪
冬ごもり母のラジオを拝借し
田中優美子
小春日や書肆に芭蕉の恋の歌
小野 雅子
山際のほのぼの明し雪蛍
森山 栄子
春風やこの頃しきりに学びたし
山田 紳助
所在なき指先かざす火鉢かな
鏡味味千代
枯木立舗道に影の黒々と
長谷川一枝
禁門の空広びろと冬の鳶
小野 雅子
冬の虹なないろすべて嘘つぽく
田中優美子
梅まつり人の流れに逆らはず
中村 道子
(梅まつり人の流れに逆らわず)
ショーウィンドウ覗いてばかりクリスマス
鏡味味千代
(ショーウィンドウ覗ゐてばかりクリスマス)
白梅に誘(いざな)はれゆく夜の径
深澤 範子
(白梅に誘はれ歩く夜の径)
やはらかき風にさそはれ梅を見に
長谷川一枝
(やはらかき風にさそはれ今日梅見)
梅白し矢来の如く足場組み
三好 康夫
(矢来思はする足場や梅白し)
毎日が綱渡りめく梅白き
千明 朋代
(毎日が綱渡りのごと梅白き)
梅ふふむここから先は知らぬ道
山田 紳助
(梅ふふむここから先は知らない道)
石蕗の花ラジオの声の漏れ聞こえ
鏡味味千代
(ラジオの声漏れ聞こえたり石蕗の花)
晴れてきて雪原の果てうす青く
小野 雅子
(晴れてきて雪原の果て青あはく)
空腹を覚えて久し着ぶくれて
島野 紀子
(着ぶくれて空腹覚ゆこと久し)
街灯にすつと浮き出る夜の梅
チボーしづ香
(街灯下すっつと浮き出る夜の梅)
「街灯下」と場所を説明する必要はありません。
子規の句碑守りてきたり臥竜梅
深澤 範子
(子規の句碑ずつと守りて臥竜梅)
時の経過を説明しすぎています。「守ってきた」と言えばずっとやってきたことがわかります。
各人が選んだ五句のうち、一番の句(☆印)についてのコメントをいただいています。
■小野雅子 選
ショーウィンドウ覗いてばかりクリスマス 味千代
防犯灯ふいに点きたる寒さかな 栄子
冬の虹なないろすべて嘘つぽく 優美子
所在なき指先かざす火鉢かな 味千代
☆天地に通へる水や梅ひらく 栄子
希望を感じます。水は地面から蒸発して天へ上り、雨や雪となって天から帰ってきます。その繰り返しの中に生き物がいて、人間も水に生かされています。厳しい寒さが緩み、春へ向かう希望の象徴として梅がひらくのだと思います。
■山内雪 選
梅園の漢手荒に古木焼べ 洋子
梅の香や足袋の踵がつと上り 康仁
冬深し塗り絵はみ出さずに塗れて 味千代
石蕗の花ラジオの声の漏れ聞こえ 味千代
☆梅ふふむここから先は知らぬ道 紳介
知らない道を歩くときの好奇心や微かなドキドキ感は進むにしたがって解れてゆく。蕾のままの梅もやがて香を放つようになる。梅ふふむに感心してしまった。
■鏡味味千代 選
梅まつり人の流れに逆らはず 道子
探梅や見知らぬ人も句帳持ち 洋子
閑谷にひびく朗唱梅の花 康仁
目薬の冷た涙のなお冷た 優美子
☆いつ止むとも知れぬ弔鐘雪もまた 雪
寒い雪の空に響く弔鐘。いつ止むとも知れないのは、鐘の音でもなく、雪でもなく、大切な人を失った悲しみと喪失感。
鐘の音にその心を託しているような、切なくなるような句である。
■藤江 すみ江 選
黄緑のにほふ瑞枝や梅蕾む 康夫
落ち葉踏む度に心の軽やかに 雅子
閑谷にひびく朗唱梅の花 康仁
禁門の空広びろと冬の鳶 雅子
☆梅の香や足袋の踵がつと上り 康仁
女性を見ている第三者がいます。 しかも焦点は踵です。梅の花が咲きゆったりとした時の流れまで感じられます。
■辻 敦丸 選
ショーウィンドウ覗いてばかりクリスマス 味千代
禁門の空広びろと冬の鳶 雅子
針先の触れし血の玉梅蕾む 康夫
石段を登りきるなり梅の花 宏実
☆梅の香や足袋の踵がつと上り 康仁
和服のご婦人が一寸背伸びし、梅の香を楽しむ様子が窺える。
■黒木康仁 選
近くまで来たと大根携へて 紳介
防犯灯ふいに点きたる寒さかな 栄子
石段を登りきるなり梅の花 宏実
天地に通へる水や梅ひらく 栄子
☆梅一輪備前に活けて客を待つ 朋代
おそらくその備前の一輪挿しは床の間に置かれたのでしょうね。お客様はどなたでしょう。ご縁談でしょうか?ご子息様が……。
■深澤範子 選
春の旅いくつもいくつも河越えて 紳介
所在なき指先かざす火鉢かな 味千代
神様はゐるのゐないの銀杏枯る 味千代
目薬の冷た涙のなお冷た 優美子
☆ショーウィンドウ覗いてばかりクリスマス 味千代
クリスマスだというのに、何も買わずにいる様子がよく見える。
■千明朋代 選
子規の句碑守りてきたり臥竜梅 範子
鯖鮓や藍絵の皿の臥竜梅 敦丸
梅の香や足袋の踵がつと上り 康仁
夜の梅既読になるも返事来ず 味千代
☆紅梅に眺めゐるのは老婆なり しづ香
紅梅に眺めいる老婦人が目にうかびました。ただ沈黙のひと時です。亡くなる母の最後の様子と重なりました。この世をおしむが如きに見ていました。
■松井洋子 選
小春日や書肆に芭蕉の恋の歌 雅子
夜の雪かすかに匂ひあるやうな 紳介
防犯灯ふいに点きたる寒さかな 栄子
禁門の空広びろと冬の鳶 雅子
☆天地に通へる水や梅ひらく 栄子
下五の「梅ひらく」を読んだ途端、初春の野に咲き初めた梅の花と、かすかな音を立てて流れ始めた水の景が浮かんだ。
天より降った雨や雪は川へ流れ込み、大海に出てまた天へ戻る。作者は春の到来を知って、この水の輪廻ともいうべき循環に思い至ったのだろう。
中七までの概念の世界から下五の目前の景へフォーカスが移るところが印象的。「ひらく」の平仮名表記も良かったと思う。
■中村道子 選
夜の雪かすかに匂ひあるやうな 紳介
老梅の精気前頭葉に受く 雅子
禁門の空広びろと冬の鳶 雅子
落ち葉踏む度に心の軽やかに 雅子
☆あの科白つい口吟む梅見かな 一枝
梅の花を見ていたら思わずお気に入りの俳優の台詞やしぐさがひょいと浮かび口ずさんでしまった。天気も上々、梅も見頃で気分も最高。
私もご一緒に梅見をしているような楽しい気持ちになりました。
■島野紀子 選
ぬくき日や応挙狗子図の梅二輪 敦丸
子規の句碑守りてきたり臥竜梅 範子
悴みて気に入りの皿また割りぬ 優美子
春風やこの頃しきりに学びたし 紳介
☆冬の夜の遠きサイレン数ふゆる 道子
私の住む街は暗く静かで夜が早い。高齢化で夜の救急車、特に冬は多い。けたたましい音がこっちにもあっちにも重なって聞こえること実景。
■森山栄子 選
子規の句碑守りてきたり臥竜梅 範子
所在なき指先かざす火鉢かな 味千代
梅ふふむここから先は知らぬ道 紳介
落ち葉踏む度に心の軽やかに 雅子
☆近くまで来たと大根携へて 紳介
近くまで来たと言うものの、持参したるは大根である。渡された瞬間、作者はその重みと瑞々しさに驚いたことだろう。土に親しむ人の飾らない人柄や、日常のささやかな喜びが自然に表現されている。
■山田紳介 選
神様はゐるのゐないの銀杏枯る 味千代
針先の触れし血の玉梅蕾む 康夫
息白し両手に重き資源ごみ 道子
梅一輪備前に活けて客を待つ 朋代
☆禁門の空広びろと冬の鳶 雅子
大らかな景、調べが美しく何度でも声に出して読みたくなる。「禁門」はその漢字からの連想でイメージが更に広がる。
私達もまた同様に「禁門」の中に生きているのかも知れない。
■長谷川一枝 選
トルソーのごとき白梅矍鑠と 康仁
閑谷にひびく朗唱梅の花 康仁
梅園の漢手荒に古木焼べ 洋子
梅の香や足袋の踵がつと上り 康仁
☆近くまで来たと大根携へて 紳介
冬の午後、夫と二人だけの昼食を終えた。会話も弾まず所在なげにテレビを見ている夫。そうだお向かいさんから大根をたくさんいただいたので、これをもって久しぶりにあの人を尋ねてみよう。お孫さんの話も聞きたいし…。そんな光景が浮かんできました。
■チボーしづ香 選
山際のほのぼの明し雪蛍 栄子
梅園の漢手荒に古木焼べ 洋子
白梅に誘(いざな)はれゆく夜の径 範子
洋服を干す手を止めて梅見かな 味千代
☆梅祭りつながれし猿何おもふ 朋代
梅と猿という一見なんのつながりのないものを祭りで繋ぐ技が冴えている。
■三好康夫 選
梅を見に光源氏の講義終へ 雪
悴みて気に入りの皿また割りぬ 優美子
白梅や待合室に香り満つ 範子
冬深し塗り絵はみ出さずに塗れて 味千代
☆石段を登りきるなり梅の花 宏実
神社の高い青空が見えました。
■田中優美子 選
ショーウィンドウ覗いてばかりクリスマス 味千代
近くまで来たと大根携へて 紳介
空腹を覚えて久し着ぶくれて 紀子
天地に通へる水や梅ひらく 栄子
☆防犯灯ふいに点きたる寒さかな 栄子
風の具合なのか、誰もいないのに防犯灯が点くことがある。冬の夜、もう眠ろうとしたときにふと明るく灯る防犯灯。
何もないと知りながら確かめに行くときの夜気の寒さと、心のうすら寒さという臨場感を覚えさせる句。
■長坂宏実 選
小春日や書肆に芭蕉の恋の歌 雅子
犬猫も皆揃ひての梅観賞 しづ香
防犯灯ふいに点きたる寒さかな 栄子
探梅の尾根へぶつかる風硬し 洋子
☆眠りたるベンチの人や梅日和 道子
ぽかぽかと暖かくなってきた日の昼間の情景が目に浮かびます。梅をながめたまま寝てしまったのは、年配のおじさんかなあと思いました。
場所や経緯を説明しすぎてしまうと、読み手の想像力を阻むことになり、余情や余韻を消してしまいます。俳句は短い詩型ですから、現実の一部分だけを思い切って切り取り、後は読み手の想像に任せましょう。
西村和子著「添削で俳句入門」(NHK出版より)
「知音」2017年5月号 窓下集 より
「知音」2017年5月号 窓下集 より
目も鼻もなき短日の木偶であり
葉書いちまい手にして湯冷めごごちかな
父を謗り母を叱りて寒や夢
おめえらと一括りされ日向ぼこ
火の付かぬ焼けぼつくいや日向ぼこ
日向ぼこ地獄見て来し顔ばかり
狡辛い男の噂日向ぼこ
羽子板市恋の迷路もなかりけり
保険証しかと確かめ初電車
初電車優先席へ迷ひなく
原稿の督促なりし初電話
加賀の雪詰めて蟹の荷届きけり
湯を花と滾らせ放ち鱈場蟹
絵師逝きしのちの開かずの障子かな
絵の奥の夜の雪積む音ひそか
目覚めけり聞こゆるはずのなき咳に
デスマスクごろんと置かれ冬館
吉田林檎
画鋲の穴あまた夜学の掲示板
井出野浩貴
湧き出でて落つるも無音秋の水
藤田銀子
小春日やトロンボーンののほほんと
高橋桃衣
小鳥来るチョコ工房はガラス張り
影山十二香
自負少し鏡に戻る秋夜かな
岩本隼人
道の辺の草の声聴く素十の忌
牧田ひとみ
正座して聴く山の音秋深し
井戸ちゃわん
朝霧がロッジの窓を流れゆく
植田とよき
出し抜けに思ひ出す名や灯火親し
石山紀代子
旅にして引鶴の空晴れ渡り
千葉美森
ためらひもなくむささびの一ッ跳び
中川純一
思いつきり尻餅つきぬ秋の雷
小原純子
島人に雁金の空あをあをと
櫻井宏平
ノーサイド円陣の背に湯気のたつ
渡谷京子
外れたる道を戻れず寒北斗
冨士原志奈
こはごはと膝の兎を撫でてゐる
大橋有美子
血涙の通へる桜紅葉かな
中田無麓
大根と大根の葉の昭和かな
高山蕗青
対岸の雪吊ふるふるふるふると
栃尾智子
真鶴や鍋鶴の飛来地として鹿児島県の出水市が知られているが、3月にもなるとまたはるばると北方の地を指して帰って行く。その繰り返しが毎年行われるのであるが、それが習性とは言いながら、何故これ程まで苛酷な旅を繰り返さなければいけないのかと思うことがある。私共人間の目から見れば、こんなに美しい水の国を去って行く鶴の気持ちが知れない、というところだろう。<鳥帰るいづこの空もさびしからむに 安住敦>の句が思い出される。
投じられた句から、車椅子での活動を余儀なくされたことが分る。また車椅子で外国にも行っている。そういう立場にあれば致し方のないことであるが、それが作句のよすがにもなるのである。上五中七、当り前のことのようであるが、これは車椅子を使用する身となっての実感なのであり、季題が有効に働いていることがポイント。
久しぶりに時間を得て故郷の母を訪れると、好物の柿を剥いてすすめて呉れた。それも山盛りにーーー。そんなに食べられないよと言いながらも母の手許をじっと見つめている作者である。