冬紅葉あきらめ方を忘れたり
月城龍二
「知音」2024年2月号 知音集 より
客観写生にそれぞれの個性を
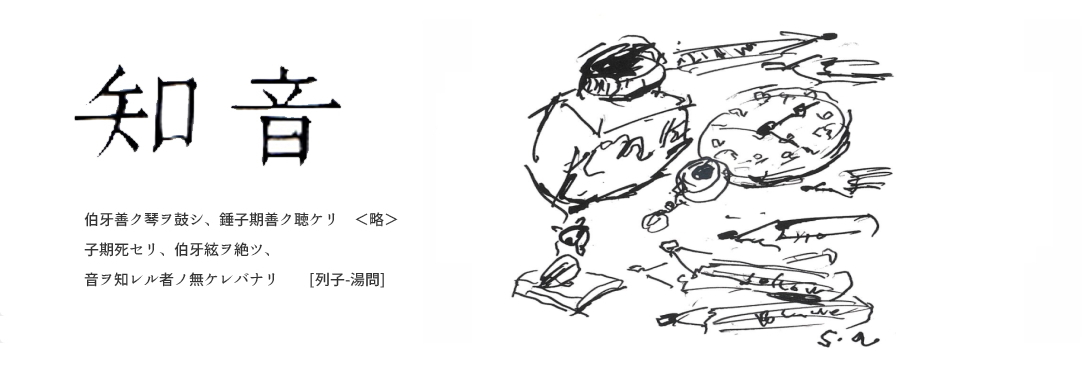
「知音」2024年2月号 知音集 より
「知音」2024年2月号 窓下集 より
「知音」2024年2月号 知音集 より
「知音」2024年2月号 知音集 より
「知音」2024年2月号 窓下集 より
「知音」2024年2月号 窓下集 より
終活の一日どんぐり拾ふなり
九月の机上終活どころではないぞ
どんぐりに打たれて馬の瞬く
どんぐり降り止まずよ人の子を抱けば
梨剝いてくるるばかりのひとでいい
柔能く剛を制すてふこと秋の風
狐の面とればきつねや秋祭
淡交といふべし濁酒銜み
生き急ぐ勿れと急かす法師蟬
釣瓶落し打出し太鼓止まぬ間に
百齢の百日過ぎし百日紅
萩叢に隠れ顔なり寺男
寺といふよりは庵の萩白し
よきにはからへ白萩の吹かれざま
酔芙蓉ゆふべの夢を手放さず
鎌倉の大路小路を秋の風
秋海棠けふの心に薄日さし
鈴虫の籠を見据ゑて父拒む
みんみんの鳴き揃ひしがずれそめし
先棒は見目好き娘秋祭
雨宿りがてらに入りて新走り
心臓は年中無休掌には梨
手に取りて俳書科学書涼新た
裏庭を覆ひ尽くせし柿落葉
八月の長押に並びたる遺影
青木桐花
名残の蓮見目美しく開きけり
山田まや
祭礼の氷川の杜の灼けに灼け
大野まりな
八月がただただ楽しかつた頃
影山十二香
敗戦忌地に一点の翳りなく
中田無麓
清め塩四隅に撒かれ花火船
田代重光
夕焼やクレヨンしんちやん年取らず
井出野浩貴
文机を窓辺に据ゑて夜の秋
牧田ひとみ
自由と孤独背中合はせの秋の昼
津金しをり
八月の京の土産の黒七味
清水みのり
八月の怒りの声と祈る声
影山十二香
飲む打つ買ふ而していま生身魂
井出野浩貴
がにまたのくせに駿足油虫
磯貝由佳子
猫の目の光りて妖し夏の宵
石田梨葡
ひとつ啼きやがてみつよつ明易し
藤田銀子
母ゆらゆら日傘ゆらゆら径白く
田中久美子
道具より十指確かや草むしる
志磨 泉
学ぶとは灸花もう摘まぬこと
大塚次郎
少女らやドレスの如く浴衣着て
佐貫亜美
子の腕我より太し夏旺ん
佐瀬はま代
「担ぎ屋」とは広辞苑には様々な意味が載っているが、最後に「野菜、米、魚などを生産地から担いで来て売る人。特に第二次世界大戦中や戦後、闇物資を運んできて売った人」とある。この句の場合は、一般的な重たい荷物を担いで来て売る人と受け取っていいだろう。その担ぎ屋が汗を拭ったとき、手首の輪ゴムに気づいたのだ。これを描いたことによって現実味が増す。その場で売るわけだから、メモや伝票をまとめるためとか、少量の売り物の袋を閉じるためとか、輪ゴムは必需品なのだろう。
「夏芝居」とは本来は歌舞伎から来た季題だが、この句の場合は現代劇かもしれない。立派な劇場ではなく、かつて養蚕所だったところで劇が上演されるという点に、地方色を汲み取ることができる。地方に限らず、東京でも倉庫を改装した「ベニサン・ピット」という劇場もあった。
養蚕という産業が廃れてしまった現代、養蚕が盛んだった地方特有の現象なのだろう。
この作者は実に様々なものに目を向け、目を止め、描いている。働く人物像も例外ではない。この句の生き生きとした、人の動きを味わいたい。
敗戦忌言葉を閉ぢる為の口
田中久美子
口は本来ものを食べる為、ものを言う為の器官だが、この句は「言葉を閉ぢる為の」と規定している。その意図を考えると、敗戦忌に臨んで何か言いたいことは山ほどあるが、言葉の虚しさを知ってしまった時には、口を閉ざすしかない、そんな思いを感じ取った。
若い頃は個性的な、夢見るような作風だった作者が、六十代を迎えて思索を深めた作風に変化してきたことを、頼もしく思う。人生経験は俳句の深まりと無縁ではないのだ。
「知音」2024年2月号 窓下集 より
「知音」2024年2月号 知音集 より
「知音」2024年2月号 知音集 より