国宝の書院の縁に梅を干し
清崎敏郎
『句集 島人』 あざぶ書房 1969刊 より
客観写生にそれぞれの個性を
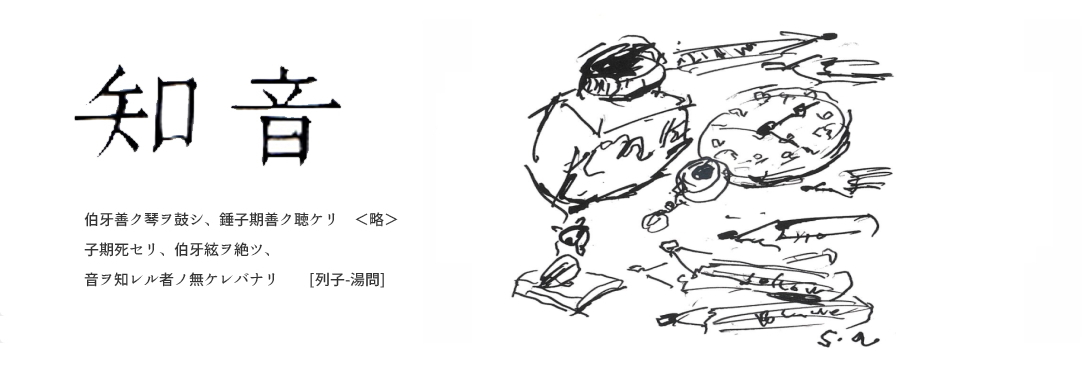
『句集 島人』 あざぶ書房 1969刊 より
『句集 昆虫記』 角川書店 1998年刊 より
見極めて新茶の緑すすりけり
ゆゆしげに古びたるなり古茶の壺
青芝の青のかぎりを返し馬
青芝の起伏耀ひファンファーレ
ダービーの穀象に鞭打つごとく
ダービーのスローモーションより抜け出す
ダービーに騎乗の昔吶々と
ダービーの夜の負犬になってゐる
走り茶の色佳し選句捗りし
注ぎ分けて新茶の滴仏にも
散り浮きてよりえごの木と気づきたり
人通り旧に復さず若葉冷
花了へし藤棚鬱を象れり
金魚雅び緊急事態など知らず
忘れられ時々愛され夜の金魚
飼ひ殺しとは罪深し金魚鉢
春マスク同士一瞥かはすのみ
中川純一
淋しさはうりざね顔の官女雛
井出野浩貴
校門のまだ開いてゐる夕桜
島田藤江
春の鴨どれも一癖ありさうな
井内俊二
砂の塔砂場に残り春の夕
植田とよき
男らは腰まで浸かり浅蜊採る
大橋有美子
春の雪夢二の墓の肩丸し
影山十二香
手秤の重み十全秋茄子
栗林圭魚
交番のここより銀座春の風
國司正夫
何もかも干してあるなり団地春
𠮷田林檎
氷解く国家瓦解の音を立て
田村明日香
芽起こしの風届かざる棺かな
志磨 泉
ふるさとに顔突き合はせ春炬燵
植田とよき
チューリップ赤いワンピースは嫌ひ
相場恵理子
目を一寸合はせそれきり卒業す
國領麻美
豆の花あなどりがたくあでやかに
中川純一
校舎より洩るるオルガンヒヤシンス
井川伸造
夜桜やこの世あの夜の裏返し
原田章代
パグ犬の鼻のちんくしや桜咲く
津田ひびき
節くれし手より楤の芽五つ六つ
染谷紀子
どのような分野の医学書か分らぬが、その最終章ははっきりと結論付けず、後考を俟つ形で終わっているというのである。
自然科学の歴史には、それまで揺るがし難い真理とされていた事象がいとも簡単に覆されてしまうということがままある。医学なども日進月歩である現在、そういうことも多かろうと思う。この句は、今世界に様々な影響を及ぼしているウイルス禍から発想された句であろう。その事を心に留めて読むと、一句の心は通じ易いが、そういう事実と切り離してみても理解できる作である。フリージアという季語が、重過ぎずに軽過ぎないペーパーウェイトのように働いている。
ところで、最近の投句の中で最も多いのは新型ウイルスに関する句である。俳人とて社会一般と人々と何ら変わるところはあり得ないので、コロナ禍は最も気に掛かることであるのは間違いない。しかし、それが即俳句になるかというと問題である。私は常日頃、「何を詠まなけばならないのか」ではなく、「何をどう詠めばいいのか」であると言い続けてきた。当面する疫病も、どう詠むか、大いに工夫を必要とするテーマなのである。
天寿を全うする、ということが言われる。作者の父君もそうであったのだろう。それが「春水の溢るるやうに」という美しい表現になった。遺された者にとって死は辛いものである。敏郎先生の長男、星野直彦さんは三十五歳でこの世を去った。慶応中等部での私の同僚であった。私の愛する古今亭志ん生の息子志ん朝は、まさにこれから脂が乗り、志ん生の芸風に拮抗してゆくだろうという時に病魔が襲った。中村勘三郎の芸は名人に近付きつつあった。彼は、踊りも芝居も「ウマすぎる」という苦言すらあった程だ。〈花道といふ道半ば冬の月 克巳〉。私も父母や祖父母の死を見送ってきた。「春水の溢るるやうに」とは本当に心が浄化される思いである。
いつ覗いても留守の日が多いのだけど、今日はめずらしく居るらしい。店の奥に灯が点っている。そこに座っている主人公の人となりが、これだけで何となく理解できる。俳句の魅力の一つ。
『句集 窓』 牧羊社 1986年刊 より
『清崎敏郎 自選三百句』 春陽堂書店 1993年刊 より
『句集 昆虫記』 角川書店 1998年刊 より
『句集 鎮魂』 角川書店 2010年刊 より
『句集 島人』 あざぶ書房 1969年刊 より
『句集 かりそめならず』 富士見書房 1993年刊 より
『句集 知音』 卯辰山文庫 1987年刊 より