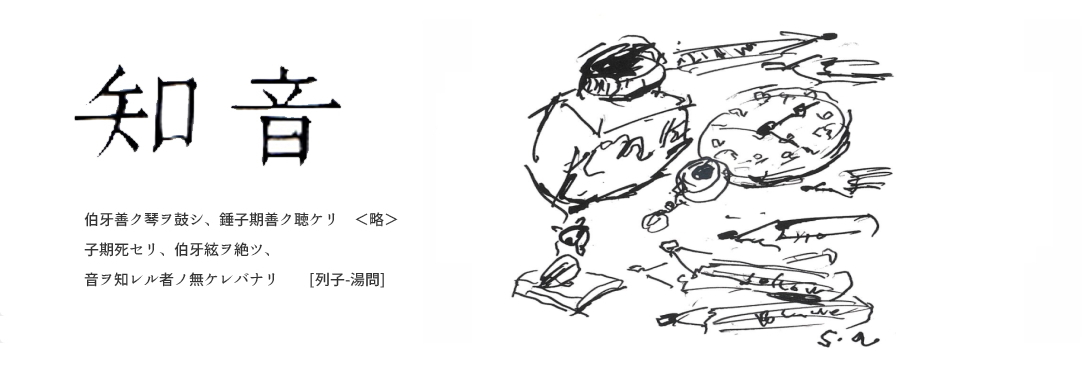◆特選句 西村 和子 選
数へ日の積読の山つみ直し
松井洋子
上質な諧謔味にあふれる一句になりました。決して整理したわけではなく、ただ単に整頓しただけで、物事の本質的な解決になっていないことを自らわかっているところに面白味があります。
誰もが経験のある行為を句材にすることは簡単なようでいて存外難しいものです。(中田無麓)
再びの単身赴任返り花
若狭いま子
ある歳時記の解説で、鍵和田秞子さんが次のように書いてらっしゃいました。「返り花の句はつねに背後に盛りの趣があって、特別に心ひかれるのであろう」。蓋し、季題の本意を言い留めておられると思いました。掲句、一見唐突に思える、単身赴任と帰り花の配合ですが、このような理解に基づいて鑑賞すると、改めてしみじみとした思いが込みあげてきます。単身赴任がご自身かご夫君かは明らかではありませんが、働き盛りを少し過ぎた頃のペーソスが伝わってくるようです。(中田無麓)
ぴょんぴょんと降りる階段冬帽子
田中花苗
一句の中で明言しなくとも、描いた人物像が具体的に見えてくる…。理想的な作句要諦の一つと言えます。掲句もその一例です。年端もいかない子どもの姿がありありと見えてきます。
その鍵を握るのが上五のオノマトペ。使い方によっては拙劣に見えてくるオノマトペは両刃の剣のようですが、巧みに用いれば、一句を読み解く重要なポイントにもなり得るのです。(中田無麓)
宇宙船めく検査室にも聖夜
松井伸子
無機質な検査室と華やかな聖夜。およそ不釣り合いの二つの言葉がどこかシンクロしている妙味のある一句になりました。検査室内ですから、ほんの小さなツリーやオーナメントなのでしょう。そこに作者は安らぎを感じているのです。不安や焦燥を否が応でも感じさせる検査室。宇宙船という秀逸な比喩も心模様を率直に表しています。(中田無麓)
葉牡丹の渦の目覚むる朝日かな
若狭いま子
「渦」という把握が巧みです。一句の中に「動」を示唆する言葉は無いにもかかわらず、生命の躍動感が伝わってきます。読み手は、渦が解けてゆく様を思い描くはずです。
17音の中に葉牡丹以外の夾雑物は一切ありません。そのシンプルで潔い句姿も、静かなダイナミズムにつながっています。(中田無麓)
クリスタル聖樹輝くカウンター
穐吉洋子
カウンターと言っても、レジカウンターのような無機質なものではないでしょう。ここは小さいけれど小洒落たバーのそれと想像したいところです。派手にクリスマスを祝うのではなく、身の丈に合った小さなツリーで祝う…。ここにマスターの美意識が働いているようです。多様な光を返すクリスタルの質感からも、物語が始まるような予感がします。(中田無麓)
一湾に汽笛重なるクリスマス
辻敦丸
一句の中に難解な字句や凝った修辞は一切ありません。至って平明な写生により詠まれた光景は雄大かつ荘重です。俳句は写生が命、の見本とも言えるでしょう。
とは言え、写生だけでは時に散漫になったり、逆に窮屈になったりすることが往々として起こりがちです。そこで必要になるのが、適切な言葉選びです。掲句では、「湾」(ここでは入江ほどの意味)というサイズ感が程よく選びきれています。湾を海や港に置き換えてみると、言葉の選択の的確さが、理解いただけるでしょう。(中田無麓)
辛さうに腰屈めたる案山子かな
板垣もと子
案山子の腰を案ずるとは、何という優しさでしょうか? 上五の「辛さうに」に、深い実感がこめられています。この実感はおそらく、ご自身か近しい方の経験を経て、始めて共感できるものだと思います。辛い経験から学べることはたくさんあります。そうして初めて、思いやりという詩ごころにつながってくるのだろうと思います。(中田無麓)
せはしなき街に留まり冬の雲
松井洋子
対比の妙が際立った一句です。静と動、天と地、卑小と偉大…。いくつもの対立構造が一句の内容を豊かにしています。解釈にあたっても、童話的な読み解きも可能ですし、黙示録的な捉え方も可能です。講評者は後者のように解釈しました。どことなく終末観が漂う句柄に時空を超越した、大きさを感じます。(中田無麓)
もう一段もう一段と毛糸編む
小野雅子
感情の含有率が高い「毛糸編む」という季題の本意をシンプルな句姿で際立たせた一句だと言えましょう。一口に「毛糸編む」と言っても、じっくりと取り組む場合もあれば、暇を見つけては編み進める場合もあるでしょうが、掲句は前者でしょう。「あと一段」という言葉が、そのゆくたてを語ってくれています。明らかにされてはいませんが、親しい誰かの編み物ではないかという、心温まる想像を掻き立ててくれます。(中田無麓)
シードルをもて成人を祝ひけり
森山栄子
シードルと言っても多岐にわたりますが、一句を鑑賞する上では、「リンゴを原料とした、アルコール度数の低いワイン」程度の理解で充分でしょう。昭和世代なら強いお酒でどんちゃん騒ぎ、一気飲みも辞さないこともしばしばでしたが、今では全く様相が異なってきているようです。
一句は「シードル」という一語の斡旋で、令和気質を軽やかに描写しています。(中田無麓)
飛行機に乗り遅れたりクリスマス
鎌田由布子
飛躍した解釈になりますが、作者はおそらく非クリスチャンでしょう。大半の日本人にとって、クリスマスとは単なるイベントの域をでず、敬虔な信仰とは縁遠いものと言えそうです。ハレとケの二分論で言えば、上五中七は「ケ」に属するもの。日常の延長線上にある(飛行機に乗り遅れることが日常では困りものですが…)日本人にとってのクリスマス観が垣間見えて、面白い一句になりました。(中田無麓)
ぞわぞわと騒く雑木や谷戸の冬
五十嵐夏美
谷戸については先月の講評でも触れましたが、掲句も同様に鎌倉の「やと」と拝察いたしました。一般的に「中七のや」は初心者のように見えるので留意が必要、とはよく言われることですが、掲句にそのような心配はありません。上五中七は、3つの自立語で成り立っていますが、その三語が緊密に連携して、一景を構成しているからです。3つの「ZO」音の連綿も一句の世界観の構成に大いに役立っています。(中田無麓)
◆入選句 西村 和子 選
駅北口通勤客の息白し
(駅北口通勤の朝息白し)
中山亮成
終点の乗客一人年詰まる
(終点にバス客一人年詰まる)
鏡味味千代
内陣の閉ざされにけり年の暮
(内陣の扉閉ざされ年の暮)
飯田静
寒禽や大楠は枝うち重ね
小野雅子
子は洗車するそれぞれの年用意
(年用意それぞれや子は洗車する)
水田和代
我先に散る散る落葉うづ高く
(我先にと散る散る落ち葉うず高く)
福原康之
一夜にて音無くなりぬ雪景色
(音無しに一夜にてなる雪景色)
深澤範子
凍蝶や玄関先にふるへをる
(小さき凍蝶玄関先にひとふるへ)
五十嵐夏美
スカーフに金風代々木の陸橋に
(代々木の陸橋スカーフに金の風)
木邑杏
銀杏散る大僧正の赤き袈裟
鈴木ひろか
夕星のはや耀ける小晦日
(夕星の早耀ける小晦日)
松井洋子
嚔して糠星ひとつ飛ばしけり
森山栄子
残る葉を揺する寒禽空真青
(残る葉を揺する寒禽真青空)
辻本喜代志
人生ゲームとんとん拍子冬うらら
(とんとん拍子の人生ゲーム冬うらら)
五十嵐夏美
息白し少女は肩で息をして
箱守田鶴
何もかも端折りて老の年用意
(何もかも端折りて老いの年用意)
若狭いま子
冬天を突き刺す屋根や本願寺
(冬空を突き刺す屋根や本願寺)
飯田静
短日や寺から寺へ早歩き
鈴木ひろか
縄跳びの止まりさう続きさう
水田和代
白き鳥陸を歩きぬ冬日和
鏡味味千代
万太郎句碑を拝して羽子板市
箱守田鶴
冬晴や遠き筑波嶺くつきりと
若狭いま子
小晦日隣近所は留守らしく
鈴木ひろか
牡蠣フライ揚げたて少し生が美味
(牡蠣フライ揚げ立て少し生が美味)
奥田眞二
雪吊や親方の指す枝に縄
鈴木ひろか
値札付くサンタクロースの贈り物
(サンタクロース値札付きたる贈り物)
飯田静
心定まり熱燗を手酌にて
小野雅子
杖を曳き雑木林の寒気浴び
(雑木林の寒気を浴びに杖を曳き)
平田恵美子
山茶花や幼馴染みのひとり欠け
(山茶花真赤幼馴染みのひとり欠け)
五十嵐夏美
クリスマスリースひときはルイヴィトン
(クリスマスリースひときわルイヴィトン)
木邑杏
乗り過ごす真夜の駅舎の聖樹かな
奥田眞二
日章旗翩翻紅葉山を背に
板垣もと子
買ひ足しにエプロン外し小晦日
小野雅子
かそけき音たてて小鳥の落葉踏む
小野雅子
首里城の完成を待ち寒桜
(首里城の完成待ちぬ寒桜)
穐吉洋子
焙煎の香のふと枯葉踏みながら
(枯葉踏みながら焙煎の香りふと)
木邑杏
年の瀬の開閉忙し昇降機
(年の瀬や開閉忙し昇降機)
穐吉洋子
肩揉むも擦るも手当て冬ひなた
松井伸子
皮手套深々と嵌め別れけり
松井洋子
電話鳴る鳴り続けたる年の暮
(電話鳴る鳴り続けたる暮新月)
福原康之
尾根かけて高舞ふ鳶や冬日和
田中花苗
キャンドルの溶けて繋がるクリスマス
森山栄子
灯台の七秒ごとの枯薄
辻敦丸
数へ日や朝の電車に人まばら
福原康之
手套を脱ぎシャッターを切りくれし
(皮手套取りシャッターを切りくれし)
松井洋子
ファミレスで夕食済ませ煤払ひ
(夕食のファミレスで済ませ煤払ひ)
鏡味味千代