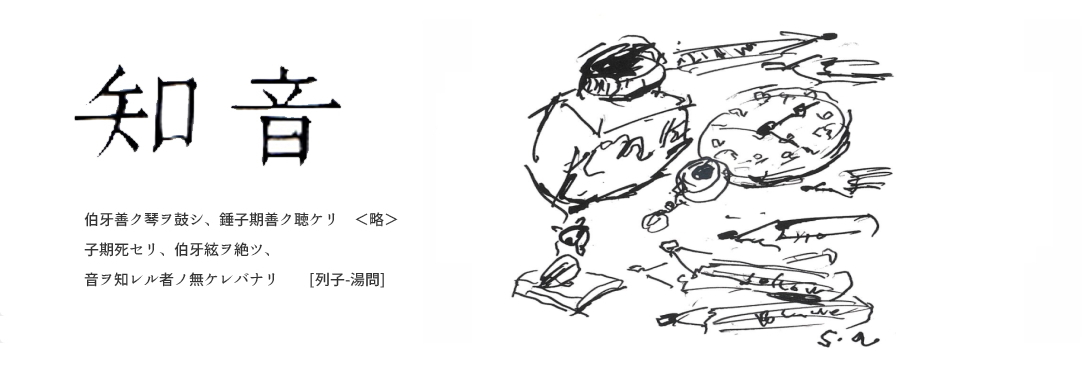負けまじく 行方克巳
気力体力財力いづれ十二月
海鼠のどこ突つついても海鼠
負けまじく極月のわが食ひ力
熊どうと倒れ一山ゆるぎけり
山眠る令和のゴジラ目覚めつつ
虚にあそび実に迷ひて近松忌
抜けがけの小才もあらず近松忌
年つまる百聞も一見もなく
箴 言 西村和子
冬に入る弓場の鏡濁り無し
大鏡磨ぐも弓場の冬支度
白足袋の足の運びも弓師範
凩に怯まず一矢番へたり
箴言は詩言に似たり落葉の碑
枯蔓の刻印あらた墓誌うすれ
日時計に遅るる冬の標準時
男の子らは絶叫疾走冬日向
目入り達磨 中川純一
紅葉且つ散るパン屋に寄りてシュトーレン
菊坂の風のすさびて近松忌
闇汁に女加はり煮えこぼれ
底抜けの冬青空の来世まで
山茶花や見慣れぬ鳥のよく鳴いて
薬局のしづかに混んでクリスマス
師の電話ぎつくり腰と小晦日
第二句集完成
大年の目入り達磨と向きあひぬ
◆窓下集- 2月号同人作品 - 中川 純一 選
束の間の小春賜り旅三日
佐藤寿子
「太陽」は女性名詞よ天高し
吉澤章子
星月夜来世は羊飼たらむ
井出野浩貴
峻烈な追慕今なほ多喜二の忌
米澤響子
見の限り潮目くつきり雁渡る
影山十二香
病室の良き香秋果もあかんぼも
佐瀬はま代
炭坑の町の消え去り紅葉山
大橋有美子
魁けて桜紅葉のためらはず
山田まや
トナカイの鼻息涎そぞろ寒
大野まりな
駅名にアイヌの響き草の花
小山良枝
◆知音集- 2月号雑詠作品 - 西村和子 選
手配写真おほかた若し秋の暮
井出野浩貴
松手入鋏持たぬ手よく動き
松枝真理子
ヴァイオリン奏で木犀ふくらませ
藤田銀子
澱みたるところ華やぎ散紅葉
牧田ひとみ
落葉踏むひとりごころを忘るまじ
前山真理
石段を下りるも遊び木の実散る
林 良子
またひとり消え逆光の芒原
中野のはら
この道をパウロ歩みき秋暑し
江口井子
表札は龍太のままに柿簾
成田守隆
六人が六人注文酢橘蕎麦
小池博美
◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子
変はらざるものこの町の冬夕焼
井出野浩貴
この町もずいぶん変わったなあという感慨は、何十年もこの町を見てきた人ならではのものだろう。句の表面では変わっていないものを詠んでいるが、景色も人々も変わってしまったことを実は表しているのだ。
「夕焼」という季語は夏のものだが、「春夕焼」「秋夕焼」「寒夕焼」のように、四季を通じて詠める季語の一つである。「冬夕焼」は西空の果に残照のように一時は燃え上がるがすぐに消えてしまう寂しい現象だ。この季語は一つの時代の終わりをも象徴しているだろう。
秋うらら江ノ電我も動かせさう
松枝真理子
こんなことを言ったら江ノ電の運転手さんに叱られそうだ。しかし、秋のうららかな一日、一輛電車の江ノ電の一番前から覗いていると、おもちゃのような電車をいとも単純に軽やかにゆっくりと運転している。なんだか私にも運転できそうという句である。単線電車の両側から、芒や萩や芙蓉の花が微笑みかけているようだ。
「江ノ電」や京都の「嵐電」といった町なかをゆっくり走る電車は俳人好みの題材だが、この句の発想は群を抜いている。
冬麗や祈祷に終はる弓稽古
牧田ひとみ
普通の弓道場ではなく、祈祷に始まり祈祷に終わる宗教にかかわる場所であろう。確か鎌倉の窓の会で出た句だから、円覚寺の境内の弓場であろう。「冬麗」という季語から、風もなく晴れ渡り、しかも空気がぴんと張り詰めた空間が想像される。稽古の終わりに仏像に手を合わせるとは、心身ともに静かな心境の持続を願ったものだろう。読み手の心もしんとしてくる。