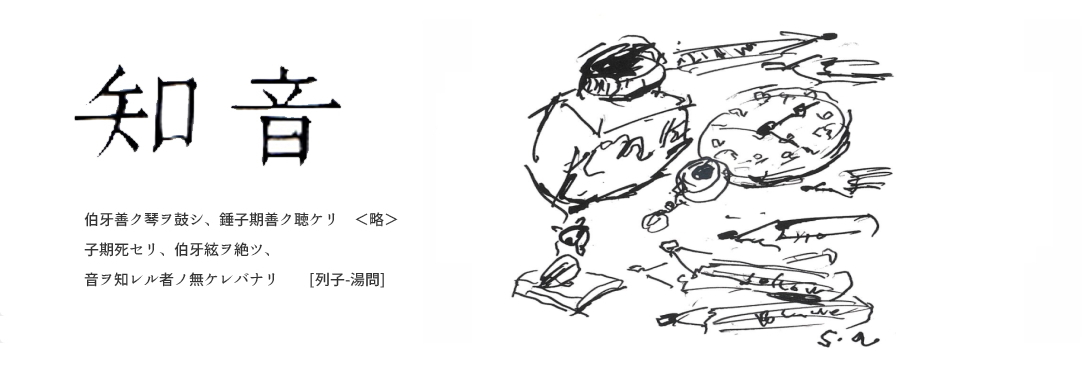一昨日の冬 行方克巳
人影のさして萍紅葉かな
紅葉且散る石のうへ水のうへ
紅葉山夜々の漆黒塗り重ね
まなうらの黄葉濃紅葉ねむりても
日めくりの一昨日の冬立ちにけり
筏なし柵なして散紅葉
綿虫や煤け給ひて祇王祇女
冬紅葉むさぼりし夜の盗汗かな
無 力 西村和子
冬ごもり根菜刻む摺る叩く
金星を吊り黄落の葡萄棚
冬草を被り果樹園養生中
石蕗の花脚下照顧といふことを
短日や煮炊忘れてもの書けば
とり消しの線の濃淡古暦
灯寒し誰も帰つてこない家
極月やもとより俳句無力なる
鷹の影 中川純一
木漏れ日踏み落葉を踏んでついてゆく
追ひ越してゆきしは鷹の影ならむ
いつ来てもいつもの守衛木の葉散る
茶の花の咲けば応へて水光る
毘沙門天訪へばいくたび時雨紅
露天湯の足をくすぐり散紅葉
冬朝日天橋立濃くしたる
冬蜂と天橋立股のぞき
◆窓下集- 1月号同人作品 - 中川 純一 選
秋日和通勤電車にて入院
松井秋尚
きちきちの跳んで将軍流離の地
井出野浩貴
鮭遡上石狩湾を引きしぼり
佐藤寿子
名月や地球大きな観覧車
橋田周子
風を食む埴輪の馬や天高し
吉澤章子
鳥渡る薄目をあけて赤ん坊
中野のはら
秋の蠅飛ぶこと忘れ俎に
小島都乎
尾を立てて犬も潜れる茅の輪かな
松井洋子
追憶は供養なりけり温め酒
佐瀬はま代
河童出る沼のほとりの曼殊沙華
吉田しづ子
◆知音集- 1月号雑詠作品 - 西村和子 選
秋刀魚焼く日曜暮るるむなしさに
井出野浩貴
色鳥やバター香らせ家を守る
志磨 泉
月今宵鉛の兵隊踊り出す
くにしちあき
鰯雲東京タワーピンで留め
栃尾智子
ひよんの笛吹きて淋しき男かな
影山十二香
西瓜切り並べて野外コンサート
山田まや
ワセリンを戸棚に探す夜寒かな
松枝真理子
虫の声違へ玄関勝手口
月野木若菜
水玉のスカート咲かせ夏座敷
加藤 爽
芋虫のどくんどくんと進みゆく
磯貝由佳子
◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子
虫の夜の孤島めきたる机かな
井出野浩貴
秋の夜更、虫の音を聴きながらひとり机に向かっている。本を読んでいるのか、ものを書いているのか、俳句を作っているのかさまざまに想像されるが、いずれにしても孤独な作業なのである。その思いがいつしか虫の音に取り囲まれて一人だけ孤島にいるような気がしてきたのだ。夜更に虫の音しか聞こえてこないという発見はよくあるが、そこから更に踏み込んで、「孤島めきたる机」と焦点を絞り込んでいるところがこの句のポイントだ。家でも部屋でもなく、机を孤島と感じているのは、孤独な作業をしている人ならではの実感である。発想はよくあることでも、どこまで深めて作品にするかが大切なのだ。
先づ手熨斗かけて羽織りぬ秋寒し
影山十二香
「秋寒」「肌寒」「うそ寒」「そぞろ寒」「朝寒」「夜寒」などは、寒いという字が使われているにもかかわらず、すべて冬ではなく晩秋の季語である。この句はその体感を実に巧みに詠み上げている。そればかりでなく、「手熨斗」「羽織る」といった美しい日本語を適切に用いている。古い言葉のようだが、アイロンをかけるまでもなく手で畳み皺を伸ばすとか、羽織を着るのではなくカーディガンやショールを上から掛ける場合にも、こうした言葉は自然に使われている。この句を音読してみると、実生活では忘れられているような佳き日本語を、俳句の上で生かしたいとつくづく思う。
落栗や前世の記憶よみがへり
松枝真理子
飛躍のある不思議な作品だが、私達の脳内や胸中にはよく起こることなのではないか。毬栗が落ちた音、あるいは落ちている光景にふと古い記憶がよみがえる、あまりにも覚束ない記憶なので、もしかしたら前世のことだったのかしら、と思う。それにしても鮮明によみがえるものがある。
こんな突飛なことは他人に話すことではない。そんなとき俳句になるのだ。季語が動くのではないかとか、共感を覚えないとか言われるだろうが、そんなことは恐れなくていい。理屈ではなく、人に納得してもらうものでもない。詩的感興にはそんな特殊な領域があって、わかってもらえる人の心には響くのだ。